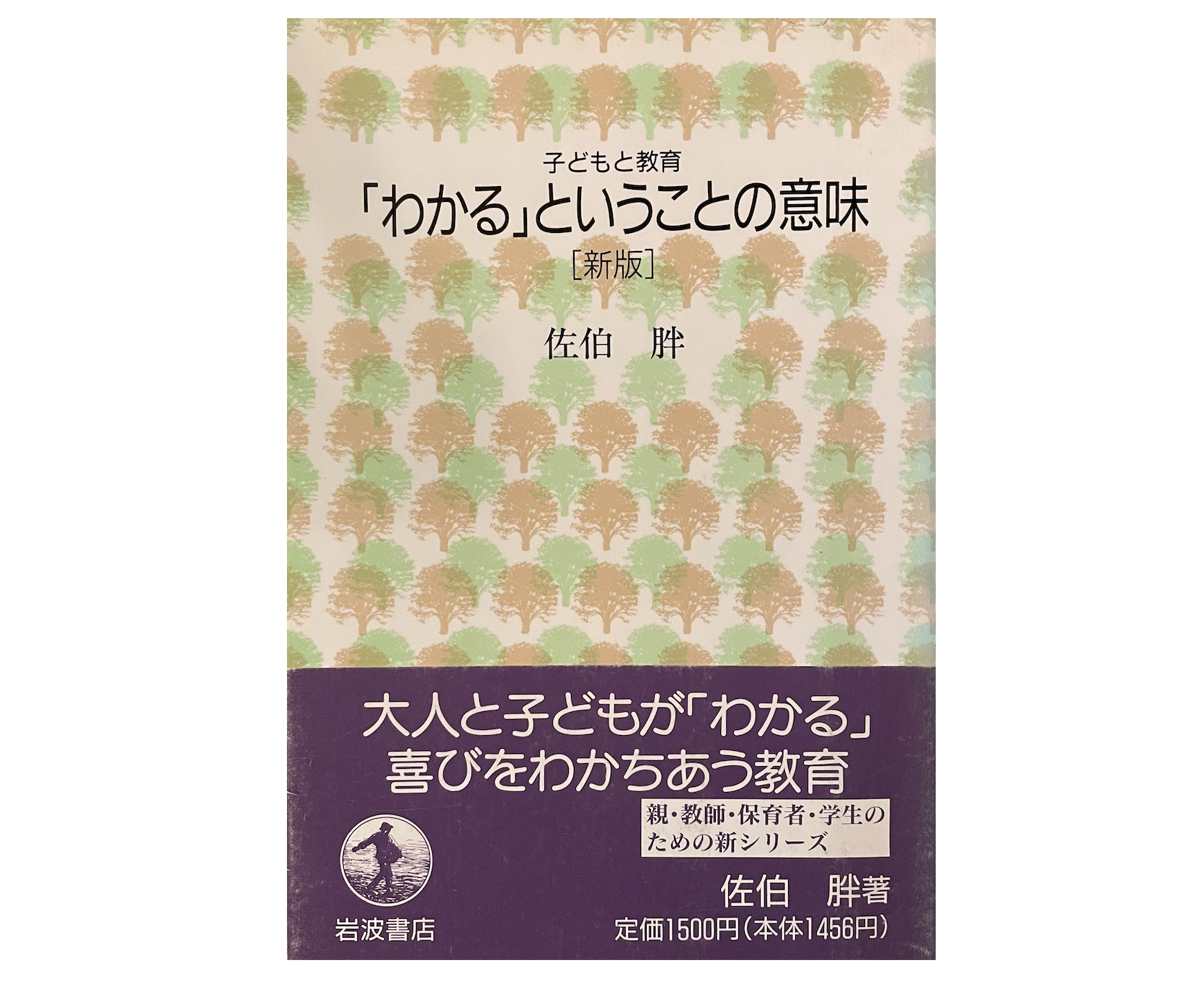佐伯胖『「わかる」ということの意味』
2023/03/30
今日はオススメ本の紹介です。
わたしが寺子屋塾を開いて間もない頃、
「佐伯さんの本を読むといいよ」と
最初に奨めて下さったのは平井雷太さんでした。
この『「わかる」ということの意味』は、
1983年に旧版が出ていたもので、
わたしが手に入れたのは1995年9月に
岩波書店から「こどもと教育シリーズ」の1冊として
新版が出たばかりのタイミングだったんですが、
初めて読んだときには、目からウロコが
100枚くらい落ちたようにおもったものです。
著者・佐伯胖(さえき ゆたか)さんは
1939年のお生まれで、
ご専門は認知科学なんですが、1981年以後は
東京大学教育学部など、主に教育のフィールドで
研究と指導にあたられてきました。
この認知科学というのは、
戦後になって生まれた比較的新しい学問で、
情報処理という観点から、生物の知の働きや性質を
理解しようとする学問らしいんですが、
佐伯さんは、認知科学の分野で得てきた成果を
教育に応用するというスタンスではなく、
教育の中に認知的な〝おもしろさ〟を見つけ
そこから認知科学の探究すべきテーマを発見し、
認知科学を深め拡大するというスタンスとのこと。
とにかく、この「おもしろい!」というのが
佐伯さんの口癖らしいんですね。
さて、そもそも「わかる」って
どういう意味でしょう?
もし、あなたが問われたらどう答えますか?
この「わかる」「わからない」という議論は、
教育者の立場から評価の側面で語られがちですが、
学習者の立場から見たときには、
「おもしろさ」「意欲」という問題と
大きく絡んできます。
本書の内容についても、タイトルから想像して、
子どもが「わかる」ために
親や先生はどう教育したらよいか、
実践的・具体的な方法が書かれているのではと
期待される方が少なくないかもしれないのですが、
残念ながらそうではありません。
たとえば、本書の序には次のような文章があります。
「子どもが思いがけずすばらしい能力を発揮したり、
こちらが予想もしなかった面で
才能を伸ばすことはよくあることです。
どんな子どもにも、きっとどこか、すばらしい面が
かくされているということは事実でしょう。
しかし、私は『子どもは無限の可能性をもっている』
ということばには、 どこか危険な考え違いが
潜んでいるように思えてなりません。
その考え違いというのは、
『教える』ということへの過信です。
どんな子どもに対しても、どんなことでも、
熱心に、情熱を注ぎ込んで、根気よく
はたらきかけさえすれば、
結局は最後にこちらの期待するような人間に
変えることができるはずだという信念です。
子どもを愛しているようでいながら、
結局のところ、
子どもを自分の思い通りに変えたがっているに
すぎないのです。」
結局のところ、「学ぶ」とはどういうことなのか?
「わかる」とはどういうことなのか?
その本質を入念に考察しようとする姿勢なくして、
人に何かを「教える」ことなど
できないのではないか、と。
人から教育者と呼ばれることがあっても
やはり迷い模索するひとりの人間にすぎないし、
何かが「わかる」ということは、
学ぼうとする者たちが主体となった、
他者との関わりの中から、
自発的に生まれるものであるはずだということが、
本書にはとても〝わかりやすく〟書かれています。
でも、〝わかる〟とは結局のところ
どういうことなのかが本当にわかった人には、
〝わかった〟などという言葉が
きっと安易に言えなくなってしまうことでしょう。
学問というものは、自分自身で、
「何が本当なのか」と本気で問うことであり、
問いつづけることなんだということを
わたしは痛感させられました。
『「学ぶ」ということの意味』とぜひセットで
読まれることをオススメします。
以下は、本書の序に置かれている
「子どもをどうみるか」後半部分からの引用です。
(引用ここから)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・・・私たち大人や教師は何でもわかっている。子どもたちだけがわかろうとしている。こんなふうに考えていたのでは、わかろうとする子どもを理解することは難しいでしょう。そうではなく、次のように考えてみてはどうでしょうか。つまり、私たちもわかろうとしている。子どもたちもわかろうとしている。そこで、一緒に、協同作業として、もっともっとわかるためにどうすればいいかを考えよう。
本書は、このように、子どもの立場にかえり、私たち自身の「わかろうとする」努力と試みの中で、子どもたちの「わかろうとする」姿をとらえようというものです。
そこで、第1部では、私たち自身が「わかっている」と思い込んでいることがいかに 「わかっていない」かについて、いろいろな事例や問題を通して「自覚」してみることにします。いきなりパズルのような問題が次々と出てきて面食らうかもしれませんが、子どもになったつもりで、一つ一つの問題を考えてみて下さい。そして、「わからない」から「わかろうとする」、さらに「なるほど、わかった!」という実感に至り、そこから「次は何がわからなければならないか」がわかってくるまで、読者自身、たどってみていただきたいのです。そのようにして、私たちも、子どもとともに、「わかろうとしている」ことに気づくでしょう。その上で、あらためて、ものごとが「わかる」ということが何であるかを考え、子どもたちが「わからない」という気持がどこから来るか、どうすればよいかを考えていきたいと思います。
第2部では、子どもが「勉強ぎらい」になったり、「やる気喪失」に陥ったりすることが、本当に「わかろうとしない」ことなのかを考えてみます。実は、心の底では「わかろうとしている」と思うのですが、どこでどうつまずいたのか、「わかろうとしない」ふりをするのです。このような考え違いをもたらしているのは、実は、「能力」ということばのもつ魔力によるのです。「能力」ということばのおそろしさをしっかりとかみしめていただくつもりです。
第3部では、スーパーマーケットの買い物客や路上でキャンディを売っている子どもたちの、いわば「直観的算数」を紹介しつつ、日常生活では人びとはけっこう「かしこく」ふるまっていることを明らかにします。つまり、どんな人でも何か「このことなら、まか してください」といえるような得意領域(「小さな世界」)をもっているのです。そして何か新しいことを理解するときには、その「小さな世界」の話と結びつけて「結局あの話と同じことだった」として理解していることを、子どもが「数」の概念を獲得していく過程を見ながら明らかにします。最後に、子どもたちに適切な「小さな世界」をつくらせ、それに慣れさせながら、しだいに「大きな数のかけ算」を理解していくという、M・ランパートさんの授業を例にして、人がものごとをわかっていくときに、意味の世界をどのように関連づけ、広げていくかを明らかにします。
第4部は本書の考え方の中心である「文化への参加」という概念について説明し、本書の全体を通した一つの考え方をまとめておきます。ここでは、「教える」ということを、知識の伝達としてではなく、文化的活動へのよびかけであり協同参加であるという考え方を説明します。私たち自身も未だ「わかっていない」存在であるとみなし、子どもたちも私たちも「わかろうとしている」ものと考え、「できること」から「わかること」へ向けて努力しながら、私たちの社会の文化をより価値ある、より人間的なものにしていこうという呼びかけが教育だというのです。そして、本書の書かれた動機も、そこにあるということをお伝えしたいしだいです。
序 子どもをどうみるか より
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
寺子屋塾に関連するイベントのご案内
4/15(土)『世界は贈与でできている』読書会 第8回
4/16(日) 第11回 易経初級講座
5/3(水・祝) 寺子屋デイ2023①
5/21(日) 第22回 経営ゲーム塾B
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー