ポップス音楽の現場から(坂本龍一・追悼)
2023/04/06
・坂本龍一 B-2 UNITS Live(NHK FM 1982.5.5)
(YouTube音源)

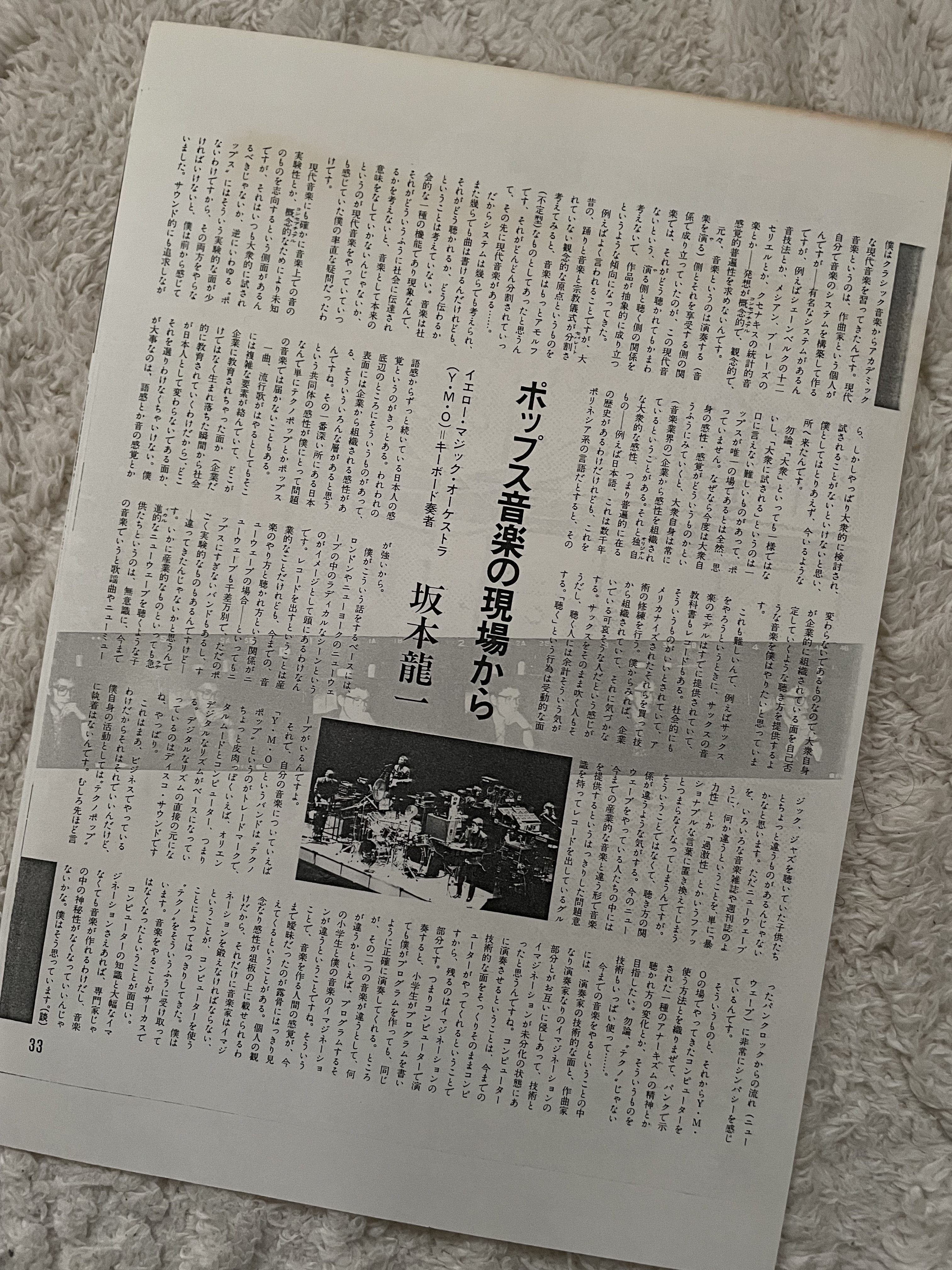
ポップス音楽の現場から 坂本龍一
僕はクラシック音楽からアカデミックな現代音楽を習ってきたんです。現代音楽というのは、作曲家という個人が自分で音楽のシステムを構築して作るんですが———有名なシステムがあるんですが、例えばシェーンベルクの12音技法とか、メシアン、ブーレーズのセリエルとか、クセナキスの推計的音楽とか———発想が概念的で、観念的で、感覚的普遍性を求めないんです。
元々、音楽というのは演奏する(音楽を演る)側とそれを享受する側の関係で成り立っていたのが、この現代音楽では、それがどう聴かれてもかまわないという、演る側と聴く側の関係を考えないで、作品が抽象的に成り立つような傾向になってきた。 例えばよく言われる昔の、踊りと音楽と宗教儀式が分割されていない観念的な原点というものを考えてみると、音楽はアモルフ(不定型)なものとしてあったと思うんです、それがどんどん分割されていって、その先に現代音楽がある。
だから、システムは幾らでも考えられ、また幾らでも曲は書けるんだけれども、それがどう聴かれるか、どう伝わるかということは考えていない。音楽は社会的な一種の機能であり現象なんで、それがどういうふうに社会に伝達されるかを考えないと、音楽として本来意味をなしていかないんじゃというのが現代音楽をやっていていつも感じていた僕の率直な疑問だったわけです。
現代音楽にも確かに音楽上での音の実験性とか、概念的なためにより未知のものを志向するという側面があるんですが、それはいつも大衆的に試されるべきじゃないか、逆にいわゆるポップスにはそういう実験的な面が少ないわけですから、その両方をやらなければいけないと、僕は前から感じていました。サウンド的にも追求しながら、しかしやっぱり大衆的に検討され、 試されることがないといけないと思いとりあえず、今いるような所へ来たんです。
勿論「大衆」といっても一様ではないし、 「大衆に試される」というのは一口に言えない難しいものがあって、ポップスが唯一の場であるとは全然、思っていません。なぜなら今度は大衆自身の感性・感覚がどういうものかというふうにみていくと、大衆自身は常に(音楽業界の)企業から感性を組織されているということがある。それと大衆的な感性、つまり普遍的に在るもの——例えば日本語、これは数千年の歴史があるわけだけれども、これをポリネシア系の言語だとすると、その語感からずっと続いている日本人の感覚というのがきっとある。われわれの底辺のところにそういうものがあって、表面には企業から組織される感性がある、そういういろんな層があると思うんですね。その一番深い所にある日本という共同体の感性が僕にとって問題なんで、単にテクノポップとかポップスの音楽では届かないこともある。
一曲、流行歌がはやるとしてもそこには複雑な要素が絡んでいて、どこか企業に教育されちゃった面か(企業だけではなく生まれ落ちた瞬間から社会的に教育されていくわけだから)、どこが日本人として変わらないである面か、それを選りわけなくちゃいけない。僕が大事なのは、語感とか音の感覚とか変わらないであるものなので、大衆自身が企業的に組織されている面を自己否定していくような聴き方を提供するような音楽を僕はやりたいと思っています。
これも難しいんで、例えばサックスをやろうというときに、サックスの音楽のモデルはすでに提供されていて、 教科書もレコードもある。社会的にもそういうものがいいとされていて、アメリカナイズされたそれらを買って技術の修練を行う。僕からみれば、企業から組織されていて、それに気づかない可哀そうな人だという感じがする。サックスをそのまま吹く人もそうだし、聴く人には余計そういう気がする。「聴く」という行為は受動的な面が強いから。
僕がこういう話をするベースには、ロンドンやニューヨークのニューウェーブの中のラディカルなシーンというのが イメージとして頭にあるわけなんです。レコードを出すということは産業的なことだけども、今までの、音楽のやり方と聴かれ方という関係がニューウェーブの場合———といっても千差万別で、ただのポップスにすぎないバンドもあるし、すごく実験的なものもあるんですけど———違ってきたんじゃないかと思うんです。いかに產業的じゃないものといっても急進的なニューウェーブを聴くような子供たちというのは、無意識に、今までの音楽でいうと歌謡曲やニューミュージック、ジャズを聴いていた子どもたちとちょっと違うものがあるんじゃないかなと思います。
ただ、ニューウェーブを、いろいろな音楽雑誌や週刊誌のように、何か違うということを、単に「暴力性」とか「過激性」とかファッショナブルな言葉に置き換えてしまうとつまらなくなってしまうんですが、そういうことではなくて、聴き方の関係が違うような気がする。今のニュウェーブをやっている人たちの中には、今までの産業的な音楽と違う形で音楽を提供するというはっきりした問題意識を持ってレコードを出しているグループがいるんですよ。
それて、自分の音楽についていえば「Y・M・O」というバンドは〝テクノポップ〟というのがトレードマークでちょっと皮肉っぽくいえば、オリエンタルムードとコンピュータ−、つまりデジタルなリズムがベースになっている。デジタルなリズムの直接の元になっているのはディスコ・サウンドですね、やっぱり。
これはまあ、ビジネスでやっているわけだからそれはそれでいいんだけど、僕自身の活動としては〝テクノポップ〟に執着はないんです。むしろ先ほど言ったパンクロックからの流れ(ニュウェーブ)に非常にシンパシーを感じているんです。そういうものと、 それから「Y・M・O」の場でやってきたコンピューターを使う方法とを織り交ぜて、パンクで示された一種のアナーキズムの精神とか聴かれ方の変化とか、そういうものを目指したい。勿論、〝テクノポップ〟じゃない技術もいっぱい使って……
今までの音楽をやるということの中には、演奏家の技術的な面と、作曲家なり演奏家なイマジネーションの部分とがお互いに侵しあって、技術とイマジネーションが未分化の状態にあったと思うんですね。コンピューターに演奏させるということは、今までの技術的な面をそっくりそのままコンピューターがやってくれるということですから、残るのはイマジネーションの部分です。つまりコンピューターで演奏すると、小学生がプログラムを書いても僕がプログラムを作っても、同じように正確に演奏してくれる。
その二つの音楽が違うとして、何が違うかといえば、プログラムするその小学生と僕の音楽のイマジネーションが違うということですね。そういうことで、音楽を作る人間の感覚が、今まで曖昧だったのが露骨にはっきり見えてくるということがある。個人の観念なり感性が俎板の上に載せられるわけだから、それだけに音楽家はイマジネーションを鍛えなければならないということが、コンピューターを使うことによって、はっきりしてきた。僕は〝テクノ〟をそういうふうに受け取っています。音楽をやることがサーカスではなくなったということが面白い。コンピューターの知識と大幅なイマジネーションさえあれば、専門家じゃなくても音楽が作れるわけだし、音樂の中の神秘性がなくなっていいんじゃないかな。僕はそう思っています。(談)
※季刊誌〝is〟vol.9 特集「音楽」より転載
ポーラ文化研究所・1980年6月10日発行
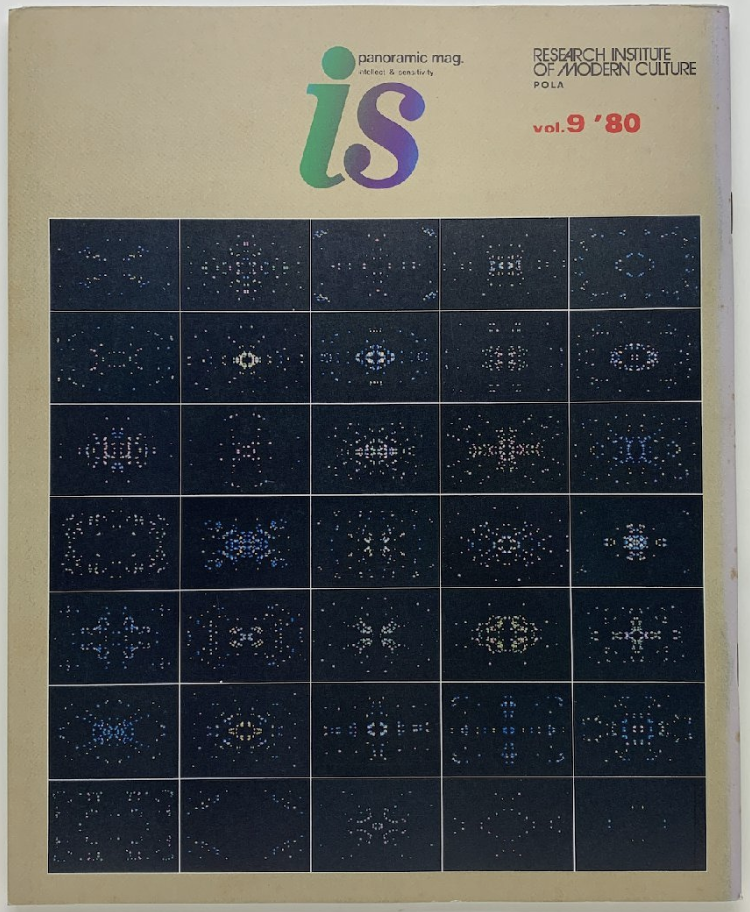
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
寺子屋塾に関連するイベントのご案内
4/15(土)『世界は贈与でできている』読書会 第8章
4/16(日) 第11回 易経初級講座
5/3(水・祝) 寺子屋デイ2023①
5/21(日) 第22回 経営ゲーム塾B
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー




