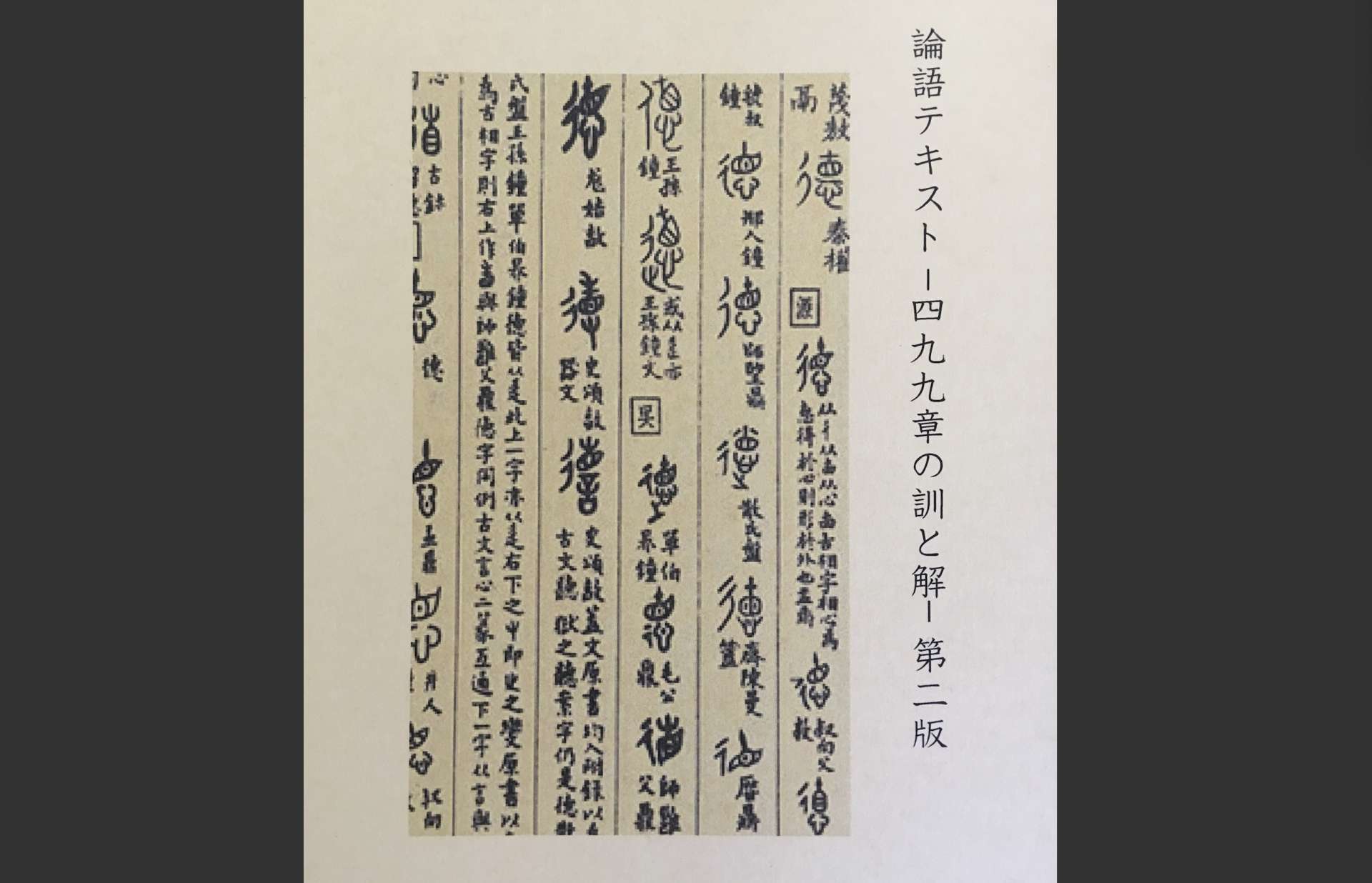一を以て之を貫く(「論語499章1日1章読解」より)
2022/02/20
日曜は古典研究カテゴリーの日です。
先週2/13の記事では、
孔子と門人・冉求との対話を書いた
雍也・第六の10番(通し番号129)を
紹介したんですが、
今日教室にやってきていた塾生と話しているときに
「一以貫之」で知られる
衛霊公第十五の2番(通し番号381)のことを
ふとおもいだしたので、
それを紹介することにしました。
----------------------------------------------
【今日の論語:No.381「衛霊公第十五」2番】
[要旨(大意)]
孔子の思想の根幹がただひとつの道で貫かれていることを、子貢との問答で示した章。
[白文]
子曰、賜也、女以予爲多學而識之者與、對曰然、非與、曰、非也、予一以貫之。
[訓読文]
子曰ク、賜ヤ、女予ヲ以テ多クヲ學ンデ之ヲ識ル者ト爲スカ、對ヘテ曰ク、然リ、非ナルカ、曰ク、非ナリ、予ハ一ヲ以テ之ヲ貫ク。
[カナ付き訓読文]
子(し)曰(いわ)ク、賜(し)ヤ、女(なんじ)予(われ)ヲ以(もっ)テ多(おお)クヲ學(まな)ンデ之(これ)ヲ識(し)ル者(もの)ト爲(な)スカ、對(こた)ヘテ曰(いわ)ク、然(しかり)リ、非(ひ)ナルカ、曰(いわ)ク、非(ひ)ナリ、予(われ)ハ一(いつ)ヲ以(もっ)テ之(これ)ヲ貫(つらぬ)ク。
[ひらがな素読文]
しいわく、しや、なんじはわれをもって、おおくまなんでこれをしるものとなすか、こたえていわく、しかり、ひなるか。いわく、ひなり、われはいつをもってこれをつらぬく。
[口語訳文1(逐語訳)]
先生(孔子)が言われた。「賜(=子貢)よ、お前はわたしを多く学んで知識のある者だと思うか。」子貢が答えて言った。「その通りです。違うのですか。」先生が言われた。「違うのだ。わたしはたった一つで貫いてきた。」
[口語訳文2(従来訳)]
先師がいわれた。――「賜よ、お前は私を博学多識な人だと思っているのか」
子貢がこたえた。――「むろん、さようでございます。ちがっていましょうか」
先師――「ちがっている。私はただ一つのことで貫いているのだ」(下村湖人『現代訳論語』)
[口語訳文3(井上の意訳)]
孔子「子貢よ、お前はわたしのことを多くの学問を修め、多くの知識を持っている人物だとおもっているのかい。」
子貢「ええ、そうです。違うんですか?」
孔子「いや、違うんだ。わたしは学者やもの知りじいさんになろうとしたわけじゃなく、ただ1つの道をひたすらに歩んできただけなのだ。もちろん、その過程でさまざまな学問を積んできたので、博識な人物であるかのように映っているかもしれない。しかし、それはあくまで結果としてなんだ。」
[語釈]
賜:子貢の名。姓は端木。子貢は字。「賜也」の「也」は呼び掛けの助字。
女:ここでは氵(さんずい)のついた「汝」に同じ。なんじ、お前の意。
識之:これを知る。
然:肯定の返答で「その通り」の意。
一以貫之:「以」は上を受け下の主題になる機能を果たす(英語でいう関係代名詞thatに同じ)。「之」は「一」を強める助辞。
[井上のコメント]
本章は、論語のなかでもとりわけ重要な章のひとつといえるでしょう。よって少々長くなりますが、わたし自身も気合いを入れてコメントを記してみることにします。
まず、「一以貫之」は、里仁第四の15番(通し番号81)にも登場しているので、参照して比較してみたんですが、そこでは「子曰、参乎、吾道一以貫之哉、曾子曰、唯、子出、門人問曰、何謂也、曾子曰、夫子之道、忠恕而已矣」となっていました。つまり、まだ門人となって日の浅い者に対し、曾子は孔子が言った「一以貫之」をわかりやすく噛み砕いたつもりで「夫子の道は忠恕のみ」と言っているわけですが、孔子からウスノロぼんくらと評された曾子が「一以貫之」をどこまで理解できていたかについては疑問があり、少なくとも「忠恕」が「一以貫之」とイコールではないことは明らかです。本章では、孔子は子貢に「多クヲ學ンデ之ヲ識ル者ト爲スカ」と問いかけた後に「一以貫之」と述べているわけですから、狭く浅い理解に留まらないよう気をつけなければいけません。
また、本章を読んでいておもいだした既出の章に、為政第二の16番(通し番号32)「子曰、攻乎異端、斯害也已矣。」があり、その章の口語訳として「学術研鑽を行う場合は、まず1つの専門分野に集中したほうが修めやすい。」と書きました。「博学のための博学は有害無益である。まずひとつに集中してその本質をつかむことだ」というのがこの章の大意と言っていいとおもうんですが、孔子の「一以貫之」の「一」は、おそらく『書経』の商書・咸有一徳編にある「徳惟れ一なれば、動いて吉ならざるなし、徳二三なれば動いて凶ならざるなし」の「一」が意識された言い回しと見てよいでしょう。徳二三・・・つまり、わたしを含め多くの人間というものは、大脳思考の性質故につい横へ横へと興味関心が広がって行きがちです。それを吉本隆明さんは「観念の遠隔対象性」と言われているんですが、自然に任せていると、事実からどんどん離れて幻想領域に入り込んでいって、それをリアルな世界だとおもいこむわけです。それで満足感が得られる人は、ある意味幸せなのかもしれませんが、断片的な知識や情報をどれだけ積み重ねても、「之ヲ識ル者」にはならないことはもちろん、無数の知識や理論を蓄えるだけでは、結局『ただの物知り』で終わってしまいかねません。
では、どうすれば「之ヲ識ル者」になれるのでしょうか。でも、J.クリシュナムルティは「どうすればいいのか?」と人に訊ねるのは最悪な質問と言っているようですが、未来に実現したい目標をおいて、その手段を問うこと自体、大脳思考のとらわれから脱していない証拠なのではないかとおもうのです。なぜなら、孔子という人間が実践した結果として生まれたものを、そのまま持って来て目標として掲げたところで、各自が現状を認識し、自分に合ったやり方をとらない限り絵に描いた餅でしかありません。げんに孔子自身は「一以貫之」を実践できた覚者であっても、顔回をはじめ、多くの門人たちが、そうした孔子の精神波動を受け継ぐことはできず、結果的に、儒教も孔子自身の教えとは似て非なるものとなってしまったのは何故かと問う必要があるようにおもうのです。
ただ、そのあたりの経緯などは、顔淵第十二の1番(通し番号279)「顔淵問仁、子曰、克己復禮爲仁、一日克己復禮、天下歸仁焉、爲仁由己、而由人乎哉」のところで触れたので、ここでは繰り返しません。孔子は、仁や礼について門人達に盛んに語りはしましたが、顔回のように優秀な人材と巡り会いながら、結果としてそれがおもうように伝わらなかったのは、釈迦の五蘊観のような物理科学的な発想や哲学がなく、数理・抽象の概念に乏しかったことも一因かもと感じました。
九去堂のこちらのページには、「一以貫之」の「一」について、自分を学者ではなく政治(家)だと主張したと記されています。たしかに孔子は、自分を役人、政治家として雇ってくれる人間を求めて諸国を旅していたことは事実と考えて間違いないでしょう、でも、孔子にとっては政治家になることはあくまで1つの手段であって最終目的ではなく、更に言えば、儒教の開祖とか、学者や教育者、思想家と呼ばれることも目的ではなく、どうでもよかったことのようにおもうので、「一」を政治と解釈すること自体は間違いだとおもいませんが、孔子が仁という言葉に対して定常的な説明をしなかったように、わたしには具体的な言葉に解釈してしまうよりは、「ひとつの道」といった言葉で抽象的に解すのが適切であるように感じました。
ここから先は余談、蛇足です。
ここまで『論語』を読み進めてきて驚いていることの1つに、わたし自身、若い頃からまじめに『論語』を学ぼうと心がけてきた人間ではなかったのにもかかわらず、たとえば、通し番号279に出てくる「克己復礼」とは、まさに自己観察であり、セルフラーニングの実践にダイレクトにつながっている話だと感じましたし、また、今日の「一以貫之」は、未来デザイン考程において、「理念設定」局面を思考プロセスの最初に置くことに関連しているようにおもえたことなど、いま寺子屋塾にて学習プログラムとして実践していることが、意外なことに、結果として『論語』でも重要に扱われているテーマにつながっていたということがあります。江戸時代にあった多くの寺子屋で、子どもたちが『論語』をテキストとして音読していたというエピソードもあり、いつかわたしの塾でも何らかの形で『論語』を学習プログラムに組み込めたらいいなと漠然と考えることはあったのですが、こういう展開になるとは夢にもおもってもみませんでした。
ちなみに、本章については、既出の章と読み合わせることで理解が深まると感じたので、ポイントとなる3章の内容(訓読文と訳文、井上のコメント)を[参考]として再録しておきます。
[参考]
【里仁・第四】081-4-15
子曰ク、参カ、吾道一以テ之ヲ貫ク、曾子曰ク、唯、子出ズ、門人問フテ曰ク、何ノ謂ゾヤ、曾子曰ク、夫子ノ道ハ忠恕ノミ。(先生が曾子に言われた。「参(しん)よ、私の生きる道は一つのことで貫いてきた。」曾子は「はい。」と言った。先生がその場を出られたあとで、門人が「どういう意味でしょうか。」と尋ねた。曾子は言われた。「先生のおっしゃる道とは、思いやりとまごころだけです。」)
井上のコメント:この章には「仁」という文字は使われていませんが、ここで孔子が曾子に語った「一つのことで貫いてきた道」を、漢字一文字で表せば「仁」となるでしょう。この「一つのことで貫いてきた道」と言った孔子の言葉の意味は、門人になって日の浅い者にはわからなかったので、曾子は、自身の思いに正直であろうとする「忠」と、他者の身の上を自分のことのように親身に思いやれる「恕(じょ)」の二文字で説明しようとしたわけです。ただ、だからといって、「仁=忠恕」と捉えてしまうと、仁への理解を狭めてしまいかねないので、これはあくまで曾子の仁についての捉え方としておいたほうがよいようにおもいました。
【述而・第七】153-7-6
子曰ク、道ニ志シ、德ニ拠リ、仁ニ依リ、藝ニ游ル。(先生が言われた。「まず、道に志すこと。そして、徳を根拠とすることで、仁に依拠でき、それを芸によって(楽しんで)実践する。)
井上のコメント:この章は、499章ある論語の中でも十指に入るくらい重要だと言われている人もあり、それに対して異論はないのですが、抽象的表現でわかりにくい章でもあります。まず、この章には主語がなく、どんな人を主語に述べようとしているのかがハッキリしていません。ただ、孔子という人は、自分が実践して確認できていないことについては、積極的には語ろうとしなかったようですし、言葉だけで理解したところで仕方の無いような内容なので、孔子自身の体験をふまえつつも、「わたしが」と明言するのを敢えて避けたようにも読めます。ただ、意味合いとしては、「君子は」を主語で語ろうとしたものという理解でよいでしょう。
全体の流れとしては、「志於道」→「拠於德」→「依於仁」→「游於藝」と4つの順序を踏むことと、大きなところから日常の実践までがつながっていることの大事さを言っている章という風に捉えると理解しやすいとおもいました。たとえば、この章全体の主旨を企業経営になぞらえると、創業(起業)の志が最初にあり、そしてその志に基づいて、経営の拠り所となる企業理念がひとつに定まり、その理念に基づく大きな方向性としての経営戦略(方針)が策定され、そして、日常の仕事レベルに落とし込んだ経営戦術(方策)があるという感じです。
「志於道」については、学而第一と為政第二で確認したように、孔子は十五歳のときに、学問の道に志したわけですし、また、「拠於德」については、為政第二の16番(通し番号32)のコメントで紹介した、『書経』の商書・咸有一徳編にある「徳惟(こ)れ一なれば、動いて吉ならざるなし、徳二三なれば動いて凶ならざるなし」の通りです。つまり、あれもやりたい、これもやりたいという徳二三でなく徳一つまり、ひとつの徳に拠り所が定まっていることで、「依於仁」と自ずと仁に依拠した行動がとれる。でも、これまで何度も触れてきたとおり、孔子は論語のなかで「仁」についての定義を明確に語っていないのは、そもそも「仁」とは、理想化された徳目として明文化されたものでなく、人と人の間に偶発的に立ち現れるものであるためで、「游於藝」つまり、「藝」とは、教養であり六芸(礼・楽・射・御・書・数)のことですから、生活のなかでの具体的に実践すること、しかも「游」、遊び心をもって自由に身を委ね、楽しむ心境が大切と理解すればいいでしょう。
ちなみに、「游於藝」は、「藝ニ游(あそ)ぶ」と訓をふるのが普通で、「藝ニ游(よ)ル」という冨永半次郎の読み方を採用しました。「游」は「由」の仮借とみて、訓がその前の「拠」「依」と同じ読み方「よる」となり、韻を踏んでいるのが面白いとおもいます。
【顔淵・第十二】279-12-1
顔淵仁ヲ問フ、子曰ク、己ニ克チテ禮ニ復ルヲ仁ト爲ス、一日己ニ克チテ禮ニ復レバ、天下仁ニ歸ス、仁ヲ爲スハ己ニ由ル、人ニ由ランヤ、顔淵曰ク、其ノ目ヲ請ヒ問フ、子曰ク、非禮視ル勿レ、非禮視ル勿レ、非禮言フ勿レ、非禮動ク勿レ、顔淵曰ク、囘、不敏ナリト雖モ、請フ斯ノ語ヲ事トセン。(顔淵が仁について質問した。先生が言われた。「自己に打ち克って礼に復帰することが仁の道である。たとえ一日でも、自己に打ち克って礼の規則に立ち返ることができれば、天下はその仁徳に帰服するだろう。仁の実践は自己に由来するので、他人に頼って実践することはできない。」顔淵がさらに質問をした。「どうか、仁徳の具体的な実践項目について教えてください。」。先生が言われた。「礼法から外れて見てはいけない、礼法から外れて聴いてはいけない、礼法から外れて発言をしてはいけない、礼法から外れて行動をしてはいけない。」顔淵が言われた。「わたしは至らない者ではありますが、先生の言葉を実行しようと思います。」)
井上のコメント:今日から顔淵第十二篇に入ります。論語では、さまざまな門人たちが、孔子に仁について問うていますが、この章は孔門の一番弟子とも言える顔淵からの問いに対してですから、孔子も最大限の配慮をもって、精一杯言葉を尽くしているように感じられ、とても重要な章だとおもいます。ただ、それだけに、この章に対する解釈もさまざまに分かれているようで、孔子の真意を汲み取っているようにはおもえないものもあり、ひとつのポイントは、「克己復礼」と記された言葉の解釈にあるようにおもいました。たとえば、「克己心」という言葉は、今日の日本でも「己に打ち勝つ」という意味でよく使われるのですが、そもそもこの「己に打ち勝つ」という言葉がいったいどういう意味なのかと問うと、なかなかハッキリとは定まっていないようにおもうからです。
孔子は、述而第七の1番(通し番号148)で、「子曰ク、述ベテ作ラズ、信ジテ古ヲ好ム、竊ニ我ガ老彭ニ比ス。(自分は古くから伝わるものを祖述しているだけで、それを自分勝手に作り替えたり、新しいものを創ろうとしているわけではない)」と記していたとおり、新しい学説を唱えようとしていたわけではなく、人間本来の姿に立ち戻ることを大事にしていたわけですから、「仁ヲ爲スハ己ニ由ル、人ニ由ランヤ」というのは、他者や外側にある社会の規律に自分を合わせようとする姿勢ではなく、自らの内在するものに自覚的になることが大切だと言っていると考えてよいでしょう。ただ、自ら内在するものとひとくちに言っても、いまの自分で意識できている部分(釈迦の五蘊観「色受想行識」の〝識[ヴィニヤーナ]〟)だけにフォーカスしても片手落ちで、心理学で言うところの無意識領域、五蘊観「色受想行識」での〝行[サンカーラ]〟を含めた人間の精神構造全体を踏まえた上での自覚が求められるようにおもうのですが、このテーマについてはこれ以上深入りすると本章の焦点からは逸脱してしまうことになるため、日を改めて詳しく書いてみようとおもいます。
子罕第九の10番(通し番号215)に「之ニ從ハント欲スルト雖モ、由末キノミ(教えについていこうとおもうのですが、どうすれば良いのかは分からないのです)。」とあったように、その章との前後関係は不明ですが、本章の孔子の言葉を顔淵がどこまで理解できたかは疑問で、顔淵がなぜ若死にしなければならなかったのかという問いととともに、継続して考えていく必要があるようにおもいました。
※2020.1.16Facebookに投稿した記事をたたき台に体裁を整え修正・追加したものです