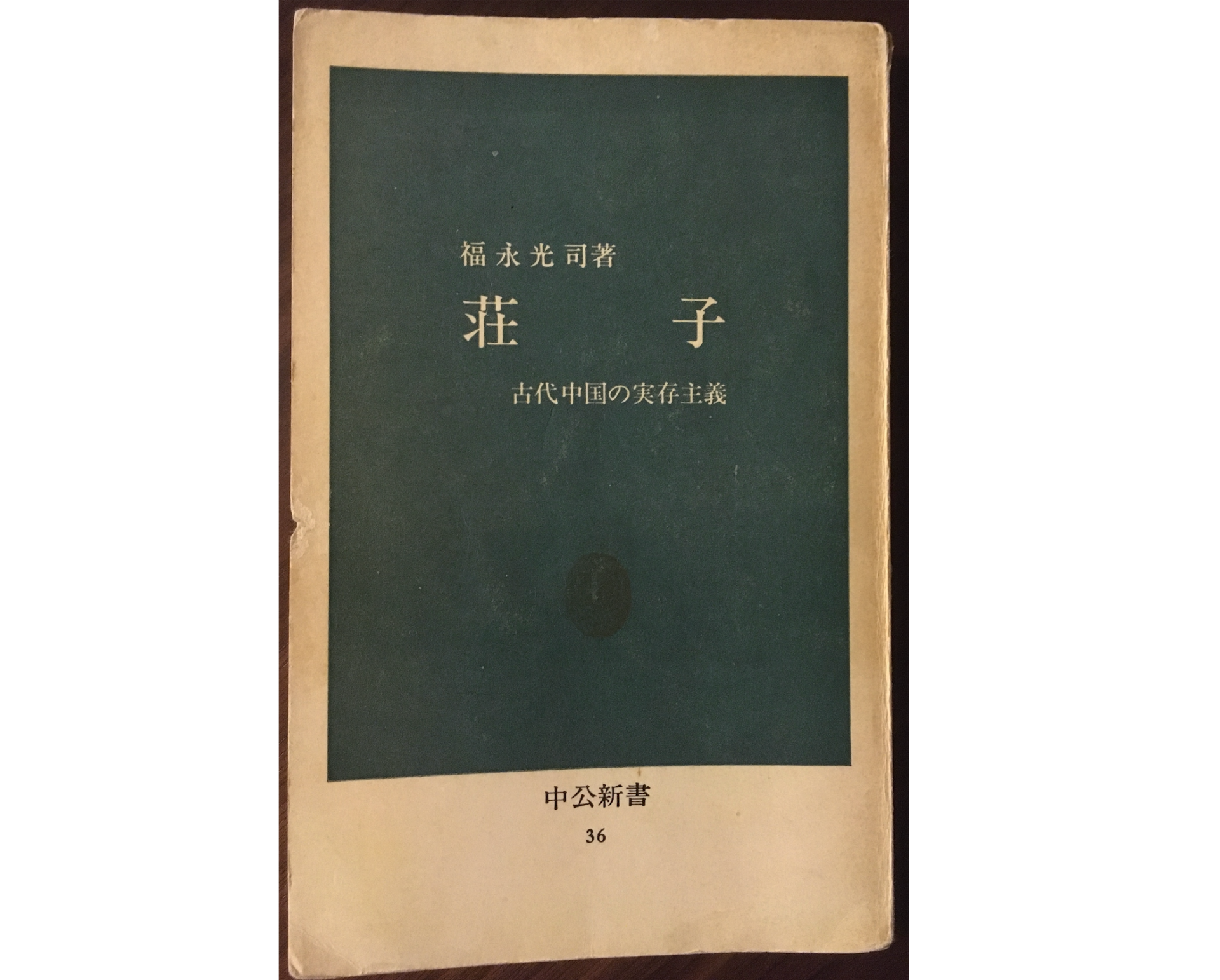福永光司『荘子 古代中国の実存主義』より
2024/03/26
昨日投稿した記事では、
「今日の名言シリーズ」として、
『荘子』の「胡蝶の夢」を取りあげたんですが、
今日も荘子についての続きを。
老荘思想研究の日本における第一人者と言われた
福永光司さんの手による
『老子』注解書の解説文から
そもそも老子とはに言及した箇所を引用し、
紹介しました。
それで今日は、福永さんがなぜ荘子に惹かれたのか、
荘子をどのように捉えているかなど、
福永さんの原点に触れることのできる文書を
ご紹介しようとおもいます。
以下、中公新書から1964年に出版された
『荘子 古代中国の実存主義』の最後にある
10ページほどの「あとがき」から
全体のほぼ半分の分量にあたる
後半部の記述を引用しました。
ちなみに、この本を入手したのは、
これまで紹介してきた
梅棹忠夫さんの『わたしの生きがい論』や
福永さんの『老子』注解書を読んだ後で、
わたしがまだ20代後半だった
進学塾で仕事をしていた頃のことです。
(引用ここから・太字は井上)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・・・荘周の哲学はその思考の奔放さにおいて、また、その規模の雄大さや言語表現の奇抜さなどにおいて、他の追随を許さない独自の境地をもつ。いわゆる〝天馬の空を駆ける〟がごとき奔放自由さをもつのが彼の哲学である。この哲学を正確に理解し、その理解を適切に説明することはきわめて困難な課題である。いうまでもなく、私のこの『荘子』はこの困難な課題に対する私の個人的な解釈、一つの理解の仕方を示すものにすぎない。そこには多くの独断や歪曲や偏見が当然指摘されるであろう。
しかし、私としてはただ現在の私が理解する私の『荘子』を、私なりの表現で説明する以外にいかなる方法もなかった。そして、私はまた『荘子』という書物は本来そのような個人的な理解や把握の仕方の許されていい書物だと考えている。唯一絶対の権威を自己の外に求めたり、古人の言説思想の奴隷となることこそ荘子の最も排撃するところであった。それぞれの人間がそれぞれに自己の人生に責任をもち、自己の足どりで自己の人生を逞しく生きてゆくことこそ荘子の哲学の根本である。
私のこの『荘子』は、私の理解し解釈する一つの『荘子』である。したがって、この『荘子』をよりよく読者に理解してもらうためには、これを書いた私という人間を『荘子』との関連において若干説明しておく必要があるように思われる。
私はうまれつき小心な人間である。幼少年時代から人間の死という問題にかなり早熟な関心をもっていた。人間の死が泣いても喚いても避けることのできない必然であることは私にも理解されていたが、死を運命づけられた人間という存在は本来いかなるものなのか、死によって断ち切られる自己の生は根源的にいかなる意味をもちうるのか、といった問題が、幼稚な思考ではあるが少年時代の私の脳裏にすでに根を張りはじめていた。
その小心な私が、祖国の名によって与えられる「死」を目前にして、懼れ怯みとまどう青年時代を過ごすことになったのも、まことに皮肉なめぐりあわせであった。自分の体にカーキ色の軍服を見いだしたときから、私は好むと好まざるとにかかわらず、この世から消えてゆく心づもりをしなければならなかった。大陸の戦場での恐怖と戦慄に蒼ざめた数年間の生活がそれに引きつづいた。『荘子』はこの時期の私にとって最も身近な存在であった。私の『荘子』に対する理解は、このような精神状況の中で培われたのである。
私が人間というものの千様万態の姿、人間の心というものの不可思議な種々相に刮目する機会を与えられたのも、かなり早い時期であった。小学校に入学する前後から私は当時の郷里の部落の風習に従って、わが家で作った野菜を4〜5キロ離れた城下町まで売りに歩いた。いわゆる振れ売りである。この振れ売りは中学校を卒業するころまで約10年間つづいたが、おかげで私は多くの市井の人々に接し、多くの家庭の台所にまで出入する便宜を与えられた。
私がもしそのころに『荘子』を読んでいたとしたら、おそらく「圏のごときものあり、臼のごときものあり、ふかきみのごときの、ひろきみのごときものあり」(『荘子』斉物論篇)と感歎したにちがいない、いろいろな人間の表情とさまざまな心の動きとがそこにあった。もったいぶったもの、つっけんどんなもの、見栄ぼうなもの、おしゃべりなもの、けちんぼうなもの等々.....福澤諭吉が少年時代をこの町に過ごして散々悪態をついている人種の末裔たちの群像であるが、しかし私にはなかなかに興味ふかい光景であった。それに、人間の社会が見かけの綺麗さや口先の上品さに似ず、 一歩家の中に入れば、複雑なかげりをもち、険しいもつれやうごめきをもつものであることも私はこのとき教えられた。
人間の社会が複雑であり、人間の心がさまざまな動きをもつのは、私の少年の日の郷里の町だけではなかった。戦場で司令部に勤務したことのある私は、そこでもまた敵を前にした将軍たちの不和と確執を見た。死を前にしたぎりぎりの状況における人間たちの憤懣と呪詛と怨恨のすさまじさを見た。それらはいずれも小心な私にとっては、気も遠くなるような光景であった。そのころの私は独り静かに『荘子』をひもといて荘周の人間理解をその行間にさぐったものである。 私の『荘子』に対する理解は、このような現実の状況の中でも培われた。
私と『荘子』との関係といえば、私は私の母のことを思い出さずにはおられない。それはまだ私が小学校の4年生か5年生のころのことであった。ある日、学校から帰った私をとらえて母が奇妙な宿題を課した。「裏の氏神の境内にある曲がりくねった松の大木が、どのようにしたら真っ直ぐに眺められるか、考えてみろ」というのである。私がもしそのとき、「その松の木を伐り倒して製材所に運べば・・・」と答えるような思考をもつ子どもであったなら、あるいはまた、母がそのような答を用意する性質の人間であったなら、私の人生と物の考え方とは、現在とは似ても似つかぬ方向をたどっていたにちがいない。
しかし、私はこの問題を解こうと本気で考えつづけるような子どもであった。ただしかし、問題は少年の私にはあまりにも高等すぎた。翌日まで考えつづけた私はついに屈服して母に答を求めた。「曲がっている木を曲がっている木としてそのままに眺めれば、真っ直ぐに見ることができる」これがそのときの母の答であったが、分かったような分からないようなこの答を聞いて、私はあっけにとられた記憶がある。しかし、この言葉は今もなお私の脳裏に生きている。私と『荘子』との結びつきが、このころからすでに約束されていたともいえる。
以上のような事情を考慮するとき、私の『荘子』に対する理解の仕方がきわめて一面的であり、 限定されたものであることを私自身みとめないわけにはゆかない。人間というものの暗さや惨めさや崩れやすさ、総じて人間存在の下限ばかりを問題にしすぎるではないかという非難も当然予想されるであろう。しかし、私はそのように非難できる人々はしあわせであると思う。そして、荘子の言い方を借りれば、そのようなしあわせな人間は現実社会には少なくて、大多数の人間は人間というものの暗さや惨めさや崩れやすさの中で日常の生活をのたうっているのである。 私はそのような人々にこの『荘子』がなんらかの参考になればと心から願っている。とともに、 私のなつかしい少年時代の思考をはぐくみ、私の出征を吹雪の中に立ちつくして見送ってくれ、 私の戦場での死を私よりも深刻に凝視したであろう故郷の母に対して、この小著を心からの感謝のしるしとしてささげたいと思う。(1964年2月 著者)
※福永光司『荘子 古代中国の実存主義』あとがきより
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(引用ここまで)
文中、わたしが勝手に太字で示した箇所
それぞれの人間が
それぞれに自己の人生に責任をもち、
自己の足どりで自己の人生を
逞しく生きてゆくことこそ荘子の哲学の根本
という見方は、寺子屋塾で実践している
「自分で決めて、自分でやってみる」
セルフラーニングの学習スタイルにつながっていて、
「自分がすべてのカギを握っている」という
転原自在の姿勢そのものと言っていいでしょう。
もちろん、「私のこの『荘子』は、
私の理解し解釈する一つの『荘子』である。」と
福永さん自身が書いているとおりで、
荘子自身がそうだったと断ずるのは早計であり、
あくまで、福永さんの理解や解釈が
そうだったというだけではあるんですが。
それと、戦場という、
死と日常的に向き合わざるを得ない
極限的ともいえる精神状況のなかで、
何より『荘子』が身近に感じられ
『荘子』に対する理解が培われたという
この福永さんの文章を読みながら、
哲学者ウィトゲンシュタインが
第一次世界大戦に志願兵として従軍しながら
『論理哲学論考』を書き上げたという
エピソードをおもいだしていました。
この話は、2023年の年間読書ふりかえりで
セレクトした24冊のうちの1冊を紹介する
次の記事に詳しく書いたんですが。
つまり、ウィトゲンシュタインは、
『論理哲学論考』草稿のなかで、
どんな状況下にあろうとも、
人が救われるアプリオリな条件とは
「認識の生を送ること」であると書いていて、
目の前で人が殺し合うような状況下においても、
人間は自分自身の認識次第で、
幸福な人生を送ることは可能であるんだと。
また、この話は福永さんが子どもの頃に
母親から貰った禅の公案のような問いへの答え
「曲がっている木を、
曲がっている木として
そのままに眺めれば、
真っ直ぐに見ることができる」
という話とも重なって、
ウィトゲンシュタインの哲学と
荘子の世界観は、
どこかで繋がっているように
わたしには感じられたのでした。
あと、最後のところで福永さんが
人間というものの暗さや惨めさや崩れやすさ、
総じて人間存在の下限ばかりを
問題にしすぎるではないかという非難も
当然予想されるであろう。
しかし、私はそのように非難できる人々は
しあわせであると思う。
そして、荘子の言い方を借りれば、
そのようなしあわせな人間は
現実社会には少なくて、
大多数の人間は人間というものの暗さや
惨めさや崩れやすさの中で
日常の生活をのたうっているのである。
私はそのような人々にこの『荘子』が
なんらかの参考になればと心から願っている。
と書かれていたことについて、
儒家と道家を総じて対比的にみたときに
傾向として言えることを
コメントしてこの記事を結ぼうとおもいます。
諸子百家の時代、中国は戦乱の世でしたから、
また、孔子には政治家を指向する時期が
長くあったことから
論語には度々政治論議が登場していましたし、
儒教(儒家)の思想には、
いかに国を治めるかという
為政者側の目線が主旋律としてあり、
礼楽的な調和的社会を理想において
現実世界の秩序を重んじる傾向がありました。
それに対し、老子荘子の道教(道家)思想には、
同じ戦乱の世に生まれたものであっても、
たとえ自分の国が戦いに敗れてしまっても、
人としていかにしたたかに生き延びるかという
庶民側の目線が主旋律としてあり、
そのために、自然と人間とを一体として貫く
統一的な理法に着目していて、
より観念的で個人主義的な傾向があった
ということは言えます。
すごく乱暴な括り方ですが、
誤解を恐れずに言うと、
儒家は右寄りな思想、
道家は左寄りな思想という側面から
捉えることも可能でしょう。
そういえば、
片方の翼だけでは鳥は飛べないってありましたね。
だから、今回5日続けて
老子や荘子ばかりを取りあげたからといって、
左が良くて、右はダメってことが
言いたいわけじゃありません。
さて、昨日今日と荘子について、
いろいろ書いてきたんですが、
これだけの文章では、
つかみどころがないなぁと感じられた方は、
松岡正剛さんの千夜千冊で紹介された
次の記事もご覧になってみて下さい。
でも、夢うつつ、無用の用、
まさに、つかみどころがないというのが、
荘子の世界観なのではとおもうんですが。笑
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●2021.9.1~2023.12.31記事タイトル一覧は
こちらの記事(旧ブログ)からどうぞ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
☆寺子屋塾に関連するイベントのご案内☆
4/6(土) 『言葉のズレと共感幻想』読書会#7