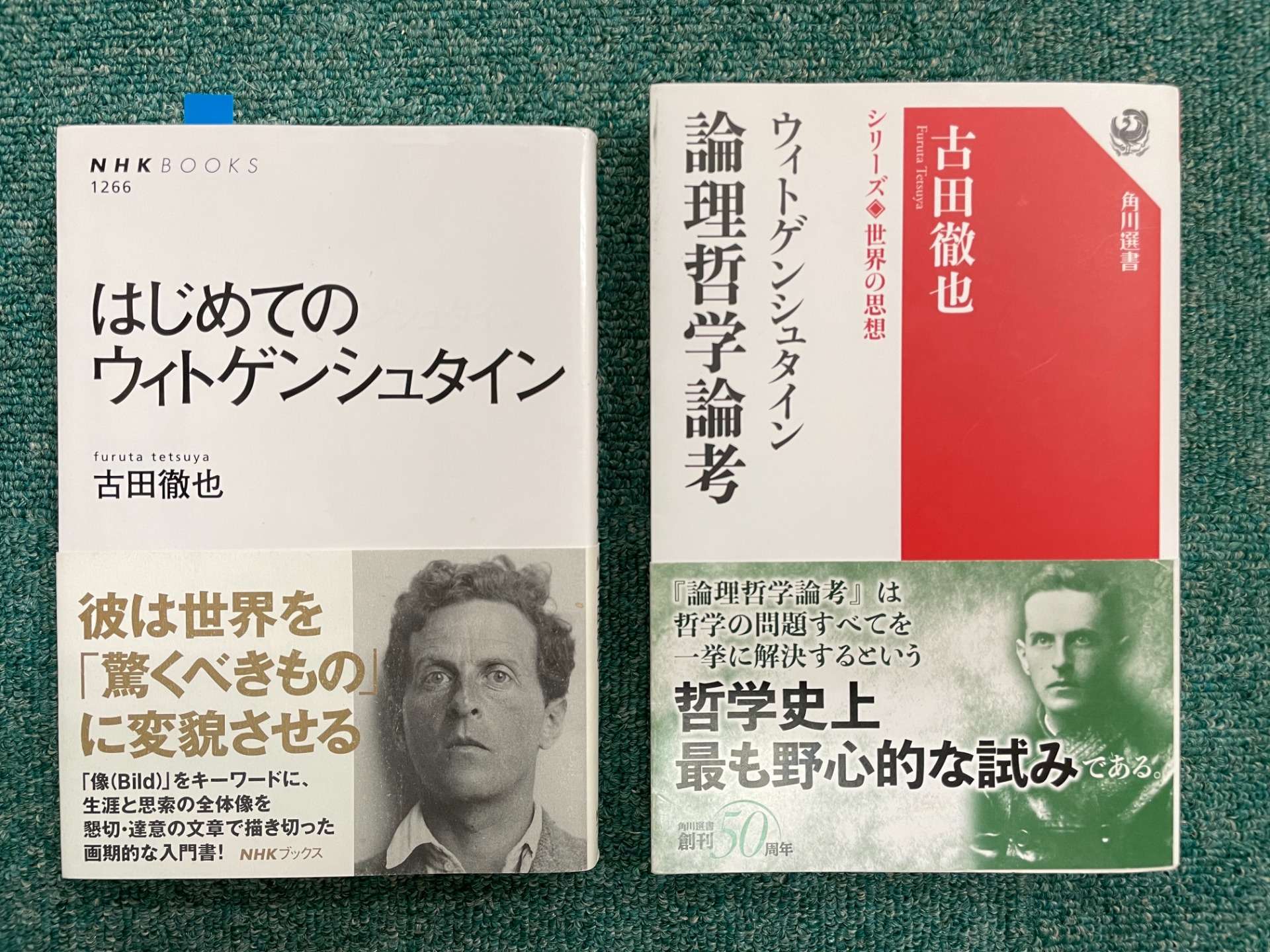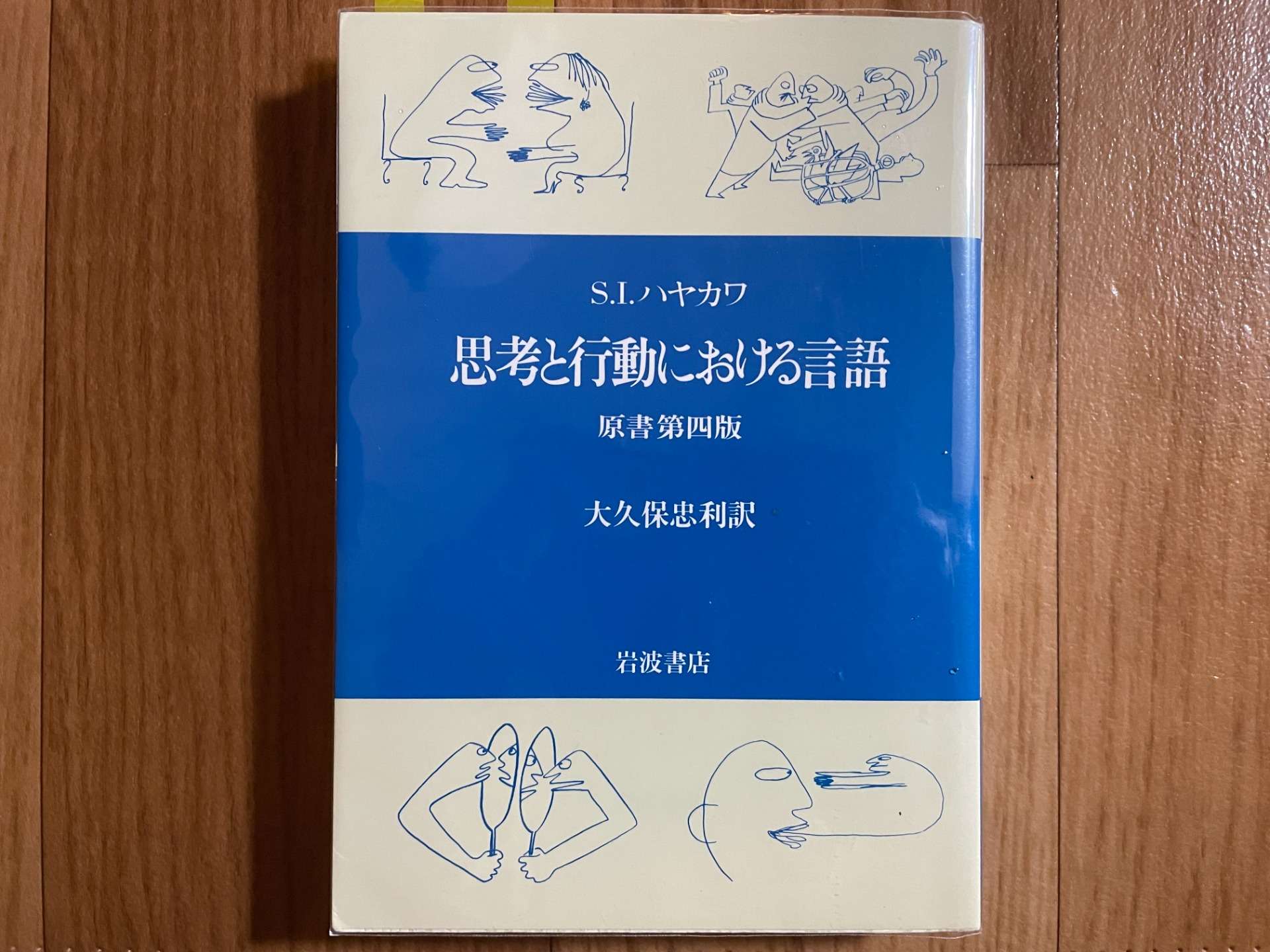古田徹也『はじめてのウィトゲンシュタイン』
2024/01/09
1/6に投稿した記事から、
年末から年始にかけて4回に分けて書いた
「2023年のふりかえり年間読書ベスト24」で
紹介した24冊の本の中うち、
このblogの記事でこれまで
あまり取りあげてこなかった本について
内容を紹介することを始めています。
1/6の記事では
1/3に投稿した(その3)の記事で⑨にとりあげた、
今村仁司編訳『現代語訳 清沢満之語録』から
「一念」と題された文章を紹介しました。
1/4に投稿した(その4)で⑲にとりあげた、
佚斎樗山(高橋有・訳&解説)『新釈 猫の妙術
武道哲学が教える「人生の達人」への道』を
紹介しています。
昨日1/8の記事では
1/3に投稿した(その3)の記事で⑮にとりあげた、
ハナムラチカヒロ『まなざしの革命 世界の見方は変えられる』を
紹介しました。
さて、4回目の今日なんですが、
1/4に投稿した(その4)で⑱にとりあげた
さきほど「このblogの記事でこれまであまり
取りあげてこなかった本」と書きましたが、
20世紀最大の哲学者のひとりと目される
ウィトゲンシュタインについては、
これまでに何度も記事に書いてきているので、
その条件からは外れてしまうんですが・・・
古田さんの本の中で、わたしが一番響いたところを
紹介する記事はまだ書いていなかったことと、
昨日紹介したハナムラさんの
「まなざしの革命、まなざしのデザイン」という
テーマからウィトゲンシュタインのことが
ふとおもい浮かんだので、
このタイミングで書いておきたいと
おもった次第です。
この記事の最後に、これまで寺子屋塾blogで
ウィトゲンシュタイン絡みで書いた記事や、
この記事の主旨と関連する記事を
整理しておきますので(たくさんあります)、
未読記事のある方は適宜参照ください。
さて、いままでこのblogで書いてきた
ウィトゲンシュタインの哲学のおさらいです。
ウィトゲンシュタインは
「哲学の役割とは何か?」と問われた際に
「ハエ取り壺に落ちたハエに出口を示すこと」
と答えています。
つまり、哲学を病人に対する〝治療〟と
考えていたわけですね。
哲学というのは、
別段高尚な学問でも何でもなくて、
健康な人間に哲学は必要ないんだと。
そして、哲学上の諸問題に対して、
そもそもそうした問題が存在するのは、
人間が言語に対する根本的な誤解があるからだと。
つまり、言語で語れることと
語れないことがあるのに、
語れないことまで語ろうとしているのが
そもそも間違いなのであるから、
ウィトゲンシュタインが
『論理哲学論考』(以下『論考』と略)で
書こうとしていたことは、
語れることの限界を示すことでした。
語れることの限界を示すことができれば
古代ギリシア時代から連綿と続いてきている
哲学上の諸問題は解決できてしまうんだと。
それで、『論考』の最後に、
およそ語られうることは明晰に語られうる。
そして、論じえないことについては、
ひとは沈黙せねばならない。
と書いたんですね。
でも、よくある誤解なんですが、
ウィトゲンシュタインは、
語れることと語れないことがあるからといって、
語れないことは大事じゃないって
言いたかったワケじゃなくて、
むしろ逆で、語れないことの方が大事であると
言いたかったんですね。
ウィトゲンシュタインは『論考』の
出版を依頼する編集者フィッカー宛の手紙の中で、
「はじめに」の中に書かれなかった文章として、
次のようなことを書いているからです。
「私はこう書くつもりでした。
私の著作は二つの部分から成っている、
一つはここに提示されているもの、
いま一つは私が書かなかったことの
すべてである、と。
そして重要なのはじつにこの第二の部分なのです」
さて、『ウィトゲンシュタイン入門』の中で、
わたしが一番響いたところはまだ書いていなかったと
先ほど書いたんですが、
その箇所を引用してご紹介します。
『論考』でウィトゲンシュタインは、
語りえないものを次々に論証していきます。
①論理
②存在
③独我論、実在論
④決定論、自由意志論
という感じなんですが、
その語りえないものたちの⑤番めに挙げられた
価値、幸福、死についての第7節をまるごと
引用しますので、
ちょっと長いですが、読んでみて下さい。
『論考』は前提としていることを積み上げながら
書いて行く哲学書なので、
この章だけを読んでも意味不明な箇所が
たくさんあるとおもいますが、
ぜひ古田さんの本を
手に取って読んで戴ければとおもいます。
(引用ここから)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
永遠の相のもとでは、世界に価値は存在しない
前節では以下の点を確認した。時間の推移とともにあるこの世界の経験的な内容を語る際には、原因と結果という関係性のもとで、個々の事態の成立や事態間の関係を記述する必要が出てくる。しかし、「かくかくの法則に従ってしかじかの加速度で石が落下した」という記述にせよ、あるいは「神が雷を落とした」とか「手をあげようと意志したから手があがった」といった記述にせよ、これらの記述の仕方がそれぞれ暗に示していること(自然法則、神、自由意志の存在)を有意味に語ることはできない。つまり、決定論も自由意志論も語りえないということだ。むしろ、『論理哲学論考』(以下『論考』と略す)でウィトゲンシュタインが強調するのは、「永遠の相」という、世界にどんな事態が実際に生じるかには全く左右されない観点のもとでは、一切は偶然に生じるものとして捉えられるということである。
世界の経験的な内容はすべて偶然の産物だ。 「世界のなかではすべてがあるようにあり、なるようになる」(論考: §6.41)。だとすれば、語りえないのは自由意志の存在や自然法則の存在、あるいは世界のあり方を司る神や運命の存在といったものだけではない。倫理や美などの価値もまた、語りえないものとなる。
この世界に生きる我々は、何らかの事態に、その事態が世界に生じることに、一定の価値を見出している。そして、それは言い換えれば、当該の事態が生じることが望ましいとか、生じるべきである、生じなければならないと考えている、ということでもある。たとえば、少なからぬ人が、核兵器は存在しない方がよい代物であり、核兵器のない社会が実現すべきだと考えているだろう。そして、その実現を目指す活動に自分の人生の意味を見出す人もいるだろう。また、ある 絵画について、それが完璧な出来だと評価し、この箇所にはまさにこの色以外にありえないとか、ここはこの構図でなければならない、と考える人もいるだろう。
しかし、本当に「すべてはあるようにあり、なるようになる」のだとしたら、世界のなかに生じるべき事態や、生じなければならない事態など、何もないことになる。世界中のすべての国家が核兵器を放棄するという事態も、ある絵画のある箇所にある色が塗られるという事態も、ただ偶然に生じたり生じなかったりするだけ、ということになるのである。この点をウィトゲンシュタインが端的に述べている一節を、以下に引いておこう。
価値と呼べるものがあるとすれば、それは、生起することども、かくあることどもすべての外になければならない。なぜなら、それらはすべて偶然的だからである。
それらを非偶然的とする何かは、世界のなかにはない。世界のなかにあるとすれば、それもやはり偶然的であることになるからである。
それは世界の外になければならない。 (論考: §6.41)
認識の生による救い
世界に生じうる事態すべてを等しく眺める永遠の相のもとでは、どの事態にも特別な重みが与えられることはない。いかなる価値も世界のなかには見出されない。幸福も、人生の意味といったものも、生起することどもの外に―――したがって、語りうることの外に差し置かれる。しかし、一見すると冷たく寂しいこの観点は、逆に、ある種の極限的な希望につながってもいる。いかなる価値も世界のなかには見出されないというのは、どんなによい事態も、それから、どんな悪い事態も、世界のなかには見出されないということである。永遠の相のもとに世界を眺める者は、この世のあらゆる善や楽しみなどを失わざるをえないが、同時に、あらゆる悪や悲しみなどからも解放される。そしてそれは、現にいま何の希望も見出せない絶望的な状況に陥っている人にとっては救いとなりうるだろう。
この点に関連して、『論考』の草稿のなかでウィトゲンシュタインは次のように綴っている。
自分の意志を働かすことはできない一方で、この世界のあらゆる苦難を受けなければならないと想定した場合、何がその人を幸福にしうるのだろうか。
この世界の苦難を避けることができないというのに、そもそもいかにして人は幸福でありうるのか。
まさに、認識の生を送ることによって。(草稿: 1916.8.13)
全く無力な状況にあり、自分の意志を働かせて世界のあり方に影響を及ぼすことが少しもできない人がいたとしよう。しかもその人は、この世界のあらゆる苦難を受けなければならないとしよう。まさに絶望的としか言いようがなく、「幸福」という言葉から最も遠いように思われるその人が、それでもなお幸福でありうるとすれば、それはいかにしてなのか。あるいは、どうすればその人生に意味を見出すことができるのか。
このウィトゲンシュタインの問いは、次のように言い換えることもできるだろう。どんな状況下にあろうとも、人が救われることはありうるのか。ありうるとすれば何によってか。すなわち、人が救われるアプリオリな条件とは何か。彼自身の答えは、「認識の生を送ること」である。では、それは何だろうか。
ここで思い起こされるのは、それこそ奴隷の境遇であっても人はなお幸福でありうるという、古代ギリシアの哲学に見られる人生観・幸福観である。その考え方によれば、観想の生にこそ人間の揺るぎない幸福はあるという。すなわち、どんな苦難に翻弄されようとも動揺せず、世界に生じる事態の一切に理や運命、神の導きといったものを見出し、泰然と受けとめる―――そうした認識に基づく生である。
ウィトゲンシュタインが、どんな境遇においても人が救われる可能性を問い、「認識の生」にその答えを求めるとき、古代の人々のこうした考え方に接近していることは間違いない。すなわち、彼がここで言う「認識」とは、彼自身の言葉でいえば、永遠の相のもとで世界全体を直観することだと言えるだろう。己の意志では世界に指一本触れられないような無力な境遇でも、己の認識次第で、世界はある意味で変わりうる。世界は、よき価値もろとも、悪しき価値もないものとなりうるのだ。
神秘は、沈黙において示され、守られる
しかし、世界をそのように捉えることは、世界のなかに生じうるあらゆる悲惨に意味を見出し、それらをそのまま肯定することにならないだろうか。―――古代ギリシアの哲学者たちがこの疑問にどう答えるかはともかく、少なくともウィトゲンシュタインは、〈永遠の相のもとで世界全体を直観する〉ということで、世界に起こりうる一切の事態を肯定する、受け入れる、ということを言っているわけではない。繰り返すように、永遠の相のもとに直観された世界には価値は存在しない。したがってもちろん、一切の事態が「よい」「然り」と肯定されることもありえないのである。
ただし、ウィトゲンシュタインによれば、それを神秘として見ることはありうる。永遠の相のもとで、世界が存在することを神秘として見ること。それは言い換えれば、世界内のいかなる事態に対しても驚き、その一切をいわば奇跡として見るということである。世界のあり方が具体的にどうであるかは全く関係ない。どんな状況であろうとも、その一切を驚きをもって、奇跡として見る、ということである。実際、ウィトゲンシュタインは後の講演「倫理学講話」においてこう述べている。
……私は、世界の存在に驚くという経験を、世界を奇跡として見る経験である、という言い方で表すことにします。(倫理学講話 p.43/393頁)
神秘は神秘に過ぎないし、奇跡は奇跡に過ぎない。だからよい(素晴らしい、美しい、等々)ということは何も帰結しない。奇跡(神秘)が歓迎すべきものだとは限らない。洪水が街を呑み込む事態も、地震が家々を破壊する事態も、人が人を傷つける事態も、あくまでも世界のなかに生じる事実という水準で見るならば、そして、永遠の相のもとに眺めるならば、すべてが等しく驚くべきものだ、ということなのである。
もっとも、世界の一切に驚き、奇跡として見ることが、絶望的な境遇にいる人を救うとは限らない。それでも、ウィトゲンシュタインはおそらく、ここになけなしの希望を見出している。逆に言えば、我々が幸福(あるいは、救い)を世界の具体的なあり方とは無関係にアプリオリに語りうるとすれば、それは〈一切を奇跡として見る〉という風にしか語りえない、そうウィトゲンシュタインは結論づけているように思われる。
しかも、それはまさに奇跡ないし神秘なのだから、実のところは語ることすらできていない。無限定の全体としての世界とは語りえないものであるし、また、そのような世界をそれとして直観している私(形而上学的な主体、哲学的な自我)も語りえない。すなわち、「認識する主体は世界のなかにはいない、認識する主体は存在しない」 (草稿: 1916.10.20)。むしろ、『論考』においてウィトゲンシュタインは、そうした「私」や「存在」といったものを語りえないものの領域に明確に位置づけることによって、それらを奇跡として保存し、その奇跡が人を――誰よりも彼自身を――救う可能性を確保しようとしている。
無限定の世界全体を直観している私について語ろうとすれば、つまり独我論を語ろうとすれば、それはたとえば自己中心主義の主張に変質してしまう。同様に、世界が存在するという奇跡について語ろうとすれば、たとえば「宇宙に生命が存在するという奇跡」や「生命を育む地球という天体が存在するという奇跡」といった、経験的な内容にまつわる話に変質してしまう。だから、語ってはならない。神秘や奇跡は、沈黙において示され、保存されるということである。
〈永遠の今〉としての現在に生きること――アプリオリに満たされた生の可能性
このように、永遠の相のもとに世界の可能性の一切を等しく見下し、一切を神秘や奇跡として見るという生――認識の生――を送る者、それをウィトゲンシュタインは「現在に生きる者」 (論考: §6.4311)とも呼んでいる。
彼の言う「現在に生きる」こととは、未来に背を向けて刹那的に生きる、などということではなく、世界に生じうる一切の事態を現在形において捉えつつ生きるということだ。言い換えれば、過去も未来もない、無時間的な生を生きるということにほかならない。
これまで繰り返し確認してきたように、永遠の相のもとに世界を捉えるというのは、時間的推移や因果的関係のなかで世界を捉えることではない以上、極めて長期間にわたって世界を捉え続けるということではない。そうではなく、まさに無時間的に、特定の時点と地点に定位せずに世界全体を眺める――可能なあらゆる事態を等しく一挙に全体として捉える―――ということだ。
したがってそこでは、〈どの事態が個別の時点と地点において実際に生じた事実であり、どの事態がそうでないか〉という区別も存在しない。言い換えれば、すでに実際に生じた事態も、まだ可能性に留まっている事態も存在しない。無時間的に捉えられた世界においては、これまであったことも、これからあるだろうこともない。いま一挙に、一切の可能性が等しくある。永遠の相のもとでは、「机の上に本がある」という事態であれ、「エベレストの山頂に三千本のペンが刺さっている」という事態であれ、可能な事態のすべてが現在形で捉えられる、ということである。 その意味で、永遠の相のもとに生きることとは、いわば永遠の今に生きること―――その意味で 「現在に生きる」ことにほかならない。そしてそれゆえ、「現在に生きる者は、恐れや希望なしに生きる」(草稿: 1916.7.14) と言いうる。なぜなら、恐れることも希望することも、まだ生じていない事態――これからあるだろうこと――の存在を前提にした態度だからである。
さらに、永遠の相のもとに生きる者には死も存在しないと言いうる。というのも、人は自分が死んだという事態を決して経験することができないからだ。それを経験するためには、人は自分自身の死の前後を見届けることができなければならない。したがって、自分の死後も生きているのでなければならない。死につつ生きている、というのは端的な矛盾であり、そうである以上、己の死というのは自分の生のなかの出来事ではありえないのである。言い換えれば、己の死とは、どこまでも可能性に留まる事態であり、〈これからあるだろうこと〉としてしか存在しえない事態だということである。
以上の点を凝縮したかたちで述べている『論考』の一節を、ここで引用しておこう。
死は人生の出来事ではない。人は死を経験しない。
永遠というものが、時間の無限の持続のことではなく、無時間性と解されるならば、現在に生きる者は永遠に生きる。
我々の生には終わりがない。我々の視野に限界がないのと同様に。(論考: §6.4311)
永遠の相のもとに生きる者―――〈永遠の今〉としての現在に生きる者―――には死は存在しない。その者は終わりのない認識の生を送る。それゆえ、死に対する不安も存在しない。それだけではない。この者には恐れも希望も存在しないし、悪しきこともよきことも存在しない。これから損なわれる可能性のあることも、これから満たされる可能性のあることも存在しない。その意味で、この者は「生きることのほかにもはや目的を必要としない者、すなわち、満たされている者」(草稿: 1916.7.6)である。しかも、この者は当然、過去に世界内に生じた何らかの事態によって満たされたわけではない。つまり、この者はアプリオリに満たされている。―――これが、言語の限界を探究する過程で〈語りえないもの〉の領域にウィトゲンシュタインが見出した、人間にとっての極限的な幸福、救いの可能性である。
※古田徹也『はじめてのウィトゲンシュタイン』第1章 第七節 語りえないものたち⑤ 価値、幸福、死など
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(引用ここまで)
昨日ご紹介したハナムラチカヒロさんの
『まなざしの革命』には、巻末に参考文献として
130冊の図書リストが掲載されていたんですが、
その中になぜかウィトゲンシュタインの本は
入っていませんでした。
それでも、ここに記されている、
どんな状況下にあろうとも、
人が救われるアプリオリな条件とは
「認識の生を送ること」である
というウィトゲンシュタインは、
まさに〝まなざしの革命〟を起こし得た人間だと
言えるのではないかと。
そして、カミュ『シーシュポスの神話』に出てくる
永遠に終わらない刑罰を科されたシーシュポスが
なぜ「すべてよし!」と語ったか、
まさにシーシュポスもまた、
まなざしの革命を起こし、
〝認識の生〟を送り得たからでしょう。
そして、永遠の今としての現在に生きる者には
死は存在しない という
一番最後に引用されている『論考』のことばは、
『論考』の中でも
わたしがとりわけ好きな言葉なんですが、
これを最初読んだときには
おもわずウルウル来てしまいました。
死は人生の出来事ではない。人は死を経験しない。
永遠というものが、
時間の無限の持続のことではなく、
無時間性と解されるならば、
現在に生きる者は永遠に生きる。
我々の生には終わりがない。
我々の視野に限界がないのと同様に。(論考: §6.4311)
ウィトゲンシュタインはこの『論考』を
第一次世界大戦中、志願兵として従軍しながら
書いたとされているんですが、
このエピソードは、彼が
オーストリア・ハンガリー帝国の首都ウィーンで
ヨーロッパ有数の裕福な家庭に生まれたことや、
4人の兄のうち3人が自殺していることとともに、
『論考』という書物を理解する上で
欠かすことのできない重要な背景だとおもいます。
目の前で人と人が殺し合うことが日常的に行われる
戦争のさなかで書かれたからこそ、
自分の意志では世界に指一本触れられないような
無力な境遇にあっても、
自分の認識次第で、世界はある意味で変わりうるし、
世界はよき価値もろとも、
悪しき価値もないものとなりうる、
そして、現在に生きる者は永遠に生きる、
我々の生には終わりがない、と書けたのでしょう。
古田さんの『ウィトゲンシュタイン入門』とともに、
『論理哲学論考』もオススメです。
【参考記事】
・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』より(今日の名言・その29)
・ウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」
・算数という教科は「算数語」という言語ゲーム
・カミュ「生きることへの絶望なくして、生きることへの愛はない」(今日の名言・その52)
・贈与読書会で40年ぶりに出会い直した『シーシュポスの神話』のこと
・『世界は贈与でできている』読書会への参加覚え書き(その1)
・『世界は贈与でできている』読書会への参加覚え書き(その2)
・『世界は贈与でできている』読書会への参加覚え書き(その3)
・『世界は贈与でできている』読書会への参加覚え書き(その4)
・『世界は贈与でできている』読書会への参加覚え書き(その5・最終回)
・9/24都内某所にOPENする「坂本図書」構想や新刊本のこと