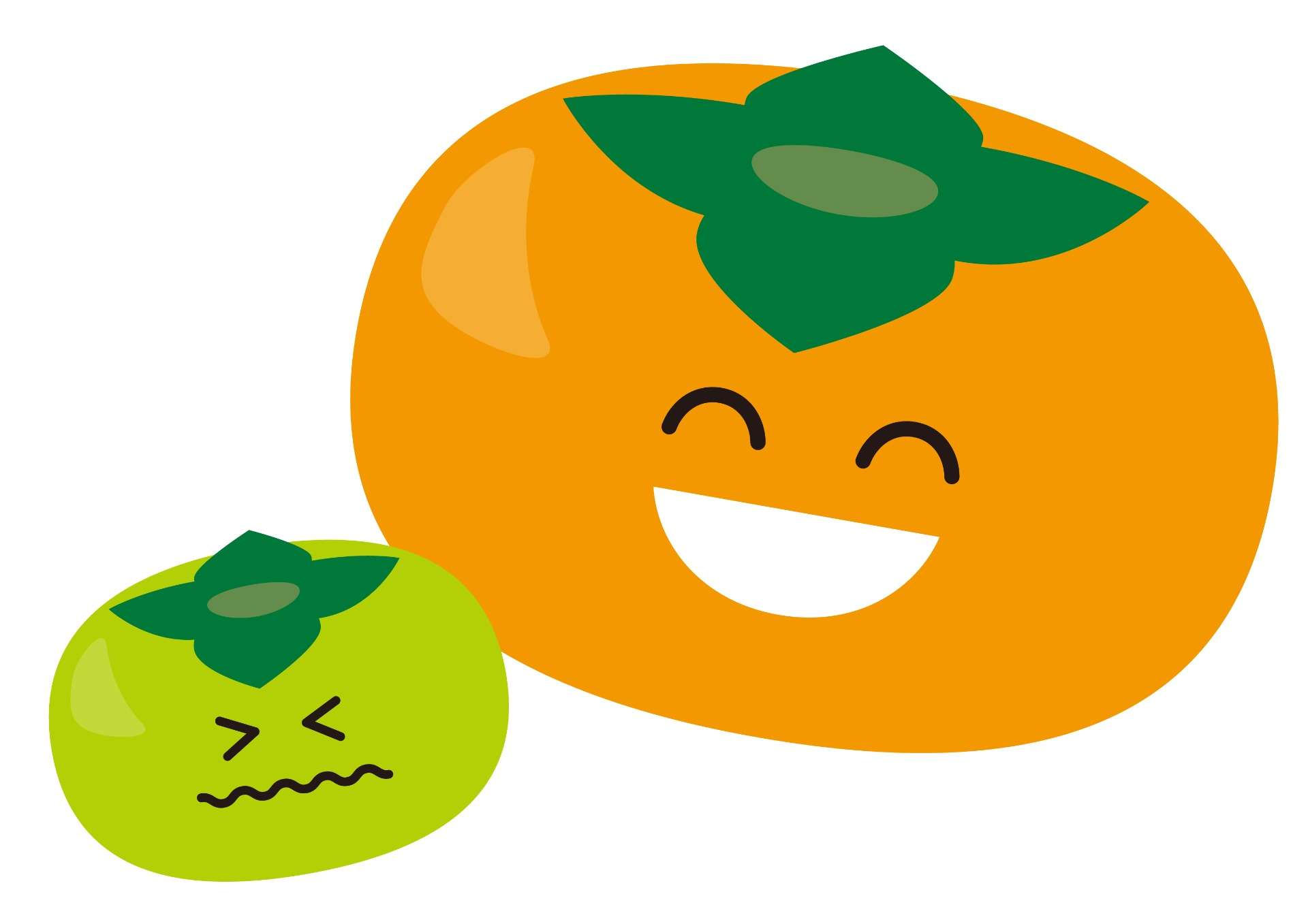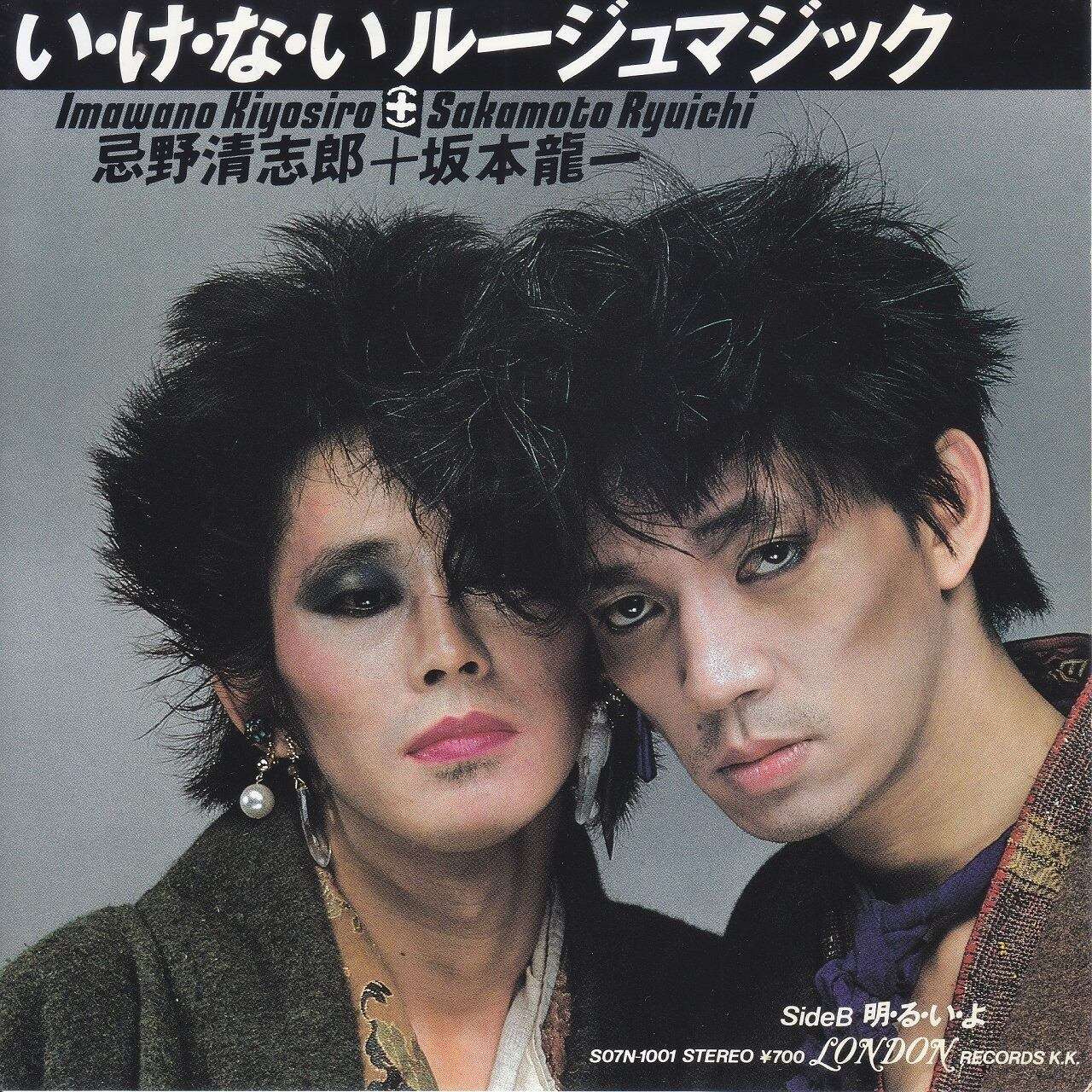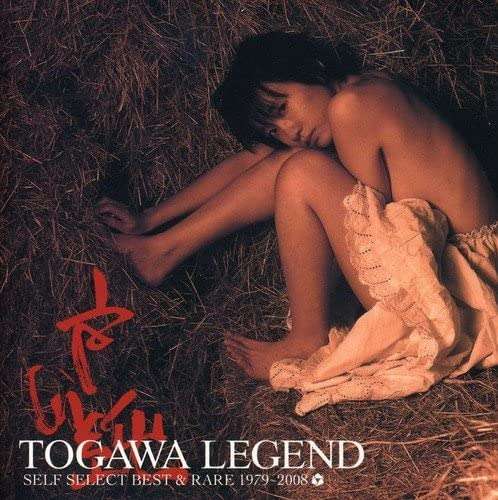陰と陽とは何か⑭「日常生活での応用(その4)食べ物にみる陰陽」
2024/06/16
6/3からこの寺子屋塾ブログでは、
「陰と陽とは何か」というテーマで投稿していて、
本日6/16の記事で14回目となりました。
①〜⑤は陰と陽のベーシックな基本事項、
⑥〜⑩は八卦の基本事項というように
中テーマ的なまとまりはあるものの、
全体でひとつらなりのことを書いているので、
以下に未読記事がある方は
まずそちらから確認下さると有難いです。
・陰と陽とは何か⑥「八卦(その1)」(易経の十翼『説卦伝』)
・陰と陽とは何か⑩「八卦(その5)」(なぜ陰が六で陽が九?)
・陰と陽とは何か⑬「日常生活での応用(その3)仁王像の不思議」
⑩まで抽象的な話が続いたので、
⑪以降では、料理の原則や文化作品の形態など
身近な話を入口にしながらも、
陰と陽の考え方を
日常生活にどのように活かし
応用するかという話を書いています。

昨日の記事では神社のコマイヌやお寺の仁王像に、
阿形(あぎょう)と吽形(うんぎょう)とが
一対になって置かれていることと
陰陽との関わりに触れる話を書いたんですが、
今日は食べ物の話に戻ろうとおもいます。
コマイヌや仁王像の左右の配置について
解き明かそうとする際には、
多くの人の利き手が右側であることや
遠心力(拡散)と求心力(凝縮)、
上昇と下降といった動きがキーワードでしたね。
物体が地球の中心に落下していく物理現象や、
液体である水を熱すれば、
気体となって蒸発していくという
化学反応にもとづいた現象があるんですが、
コマイヌや仁王像の左右の配置と同じで
普段はそうした事柄は余りにあたりまえすぎて
意識にのぼることなく
通り過ぎてしまいがちです。
でも、コマイヌの話が
食べ物とどう結びつくのかについては、
まったく想像できない方が少なくないでしょう。
したがって、一見まったく関係ないような
そうした現象の背後にある見えない法則性が、
わたしたちの食べ物に様々な影響を
与えているという話を書こうとしてるんですが。
こんにちわたしたちは、タンパク質であるとか、
カロリーであるとか、食品添加物であるとか、
いわゆる栄養学的な見地から、
食べ物を捉えたり考えたりすることはあっても、
『易経』の〝陰と陽〟という変化の哲学として
食べ物をとらえる様な機会は
めったに無いようにおもわれますので。
以下、『陰陽でみる食養法』第5章から
食べ物について書かれた箇所から
引用してご紹介しましょう。
今日の話は、いわゆる常識的な範疇には
ほとんど話題に上らない内容のものですし、
マクロビオティックの陰陽表現なので、
易経の陰陽表現とは
逆になっている箇所があることに
引き続き注意しながら読んでいってください。
(引用ここから)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
6.ゆるめる食物、ちぢめる食物
柔らかくゆるめる食物
食べものには組織をゆるめ、あるいはふくらますものと、組織をひきしめ、あるいはちぢめるものとがあります。こんなことをいうと、食べものにそんな作用があるはずはないという人がいるでしょうが、栄養学の知識にはそんな発想はまったくありませんし、現代人はおおむね西洋栄養学の観点に立ってしか食物を見なくなってきていますから、無理ないことです。
しかし、そのように栄養学の立場に立ってしか食物を見られない方も、つぎのようなことには不思議さを感じられるだろうと思います。大福餅は餅米で作ってあんこが入れてあり、お正月のあん入り餅も同じものなのに、なぜ大福餅は皮が固くならず、何日間も柔らかいままであり、お正月の餅はすぐに固くなってしまうかということです。「お正月のあん入り餅は皮は厚いけれども、大福餅は皮がうすいから、正月餅は固まりやすく、大福餅は固まりにくいのだ」という答えがあるとすれば、それは当たっていません。皮が薄ければ、かえって早く乾燥して固くなるからです。正月餅でも、あんこのところだけは固まらないでいます。大福餅には餅米に片栗粉が入っているから柔らかいのです。ということは、ジャガイモ澱粉としての片栗粉は、なかなか固まりにくい性質をもっているのです。
私の家では、お正月に毎年ふつうのお餅と黒砂糖入りのお餅を親戚からいただきます。この黒砂糖入り餅もなかなか固くなりません。いったん固くなっても、この黒砂糖入り餅とふつうの餅とを一緒に焼いてみますと、おもしろい違いが見られます。どちらが早く焼けて柔らかくなるかといえば、黒砂糖入り餅の方です。黒砂糖はもちろん、白砂糖入りも同じです。ジャムを作るとき、砂糖を入れると早く柔らかく溶けます。 あんこもおはぎもぜんざいも、砂糖を使うと小豆はより柔らかくなるのです。反対に塩をたくさん使ったら、小豆はなかなか柔らかくなりませんし、味も台なしです。
ひきしめ固くする食物
シベリアで半年以上も毎日、大豆を主食にあてがわれたことがあり、また、数ヵ月間小豆を主食にあてがわれたことがあります。大豆も小豆もともにタンパク質が多いものなのに、その生理作用はたいへん違ったものでした。大豆が主食だと、塩気がきつくないと食べにくいし、小豆が主食だと、塩気が薄くなければ食べにくいのでした。両方ともにおなかが張るものでしたが、大豆の方がより容易におなかが張り、ガスもよく出て、その悪臭にはいたく悩まされたものです。
砂糖やジャガイモ澱粉が餅を固くしにくいということは、ゆるめる作用をもっているということであり、塩が小豆を柔らかくしにくく、野菜の煮しめに用いるように、塩はものを固める作用をもっています。道路のコンクリートに塩をまぜると固くなりやすいのは、だれでも知っていることでしょう。
味で見るゆるみとちぢみ
この食物ののびる、ちぢむの見分け方の一つとして、味による顔のゆるみとちぢみを見る見方があります。味には辛い、酸っぱい、甘い、鹹い、苦い、渋いの六味があり、だれにもいやがられる味にえぐみがあります。この六味を辛酸甘鹹苦渋(しん、さん、かん、かん、く、じゅう)と音読みすると、味の陰性から陽性への秩序をもって覚えやすいものです。
辛は胡椒の辛さで、胡椒を口にすると口を大きくあけてホウホウいわせます。酸は夏みかんのような酸っぱさで、これまた口をパッと開かせます。甘は砂糖や蜜のような甘さで、口を幼児のウマウマのようにかわいく開かせ、鹹は塩辛さで、口を開かなくさせます。苦はフキノトウやニガ瓜のように口をへの字にひきしめて、白い歯を見せなくさせます。渋はシブ柿を食べたときのように顔中がクシャクシャにちぢんでしまいます。
従って、味にはロをアングリ開かせる陰性の味から、口をへの字にむすばせる陽性の味まであるわけです。えぐみというのは、フカシジャガイモの青いところを食べたときに感じる、あのなんともいえない、口が開いてゆがんでしまう味で、これも口を開かせる点で陰性の強い味で、いわゆるアクというのがこれに当たります。
流産やひきつけのもと
こうした特性をもつものを片寄ってとっていますと、つい体もそのように片寄ってくることになります。砂糖や果物などを多くとっていると、組織がゆるんで流産しやすくなったり、テンカンになったり、ヒキッケを起こしたり、肩がこったり、コムラガエリが起こりやすくなったりします。いわゆるヒキッケは、硬直と弛緩の連動作用ですが、硬直というのは組織がのび切った状態です。肩がこるというのは、節肉がのび切った状態で、水が凍ったら膨張して固くなるようなもので、一種の凍結状態ということができます。その証拠に、圧力を加えてもんだり、熱い湿布をするとほぐれるのです。
人が死んだら硬直します。これものび切った状態です。ですからケンカなどで「のすぞ」などというのは、ぶっ叩いて立ち上がれないようにグッタリのばしてしまうぞと脅かしているわけです。食べすぎて胃下垂になるのは、胃がのびて垂れたことをいい、腸捻転は、腸がのびて、ちょうど両端をもって垂らした紐がキリキリと捩(よじ)れあうことがあるように、ちょっとしたはずみに捩れるのをいうわけです。こんなふうに、食べものの質や量のとり方ひとつで、私たちの生活はゆるんだり、ふくれたり、あるいはひきしまったり、ちぢんで弾力性をもったりすることになります。
固さというもの
前に記したように、固さというものは何もひきしまったものばかりでなく、水が凍って固くなり、膨張したような場合もあるわけです。風船玉は空気を入れる前はグニャグニャで皮の厚いものですが、空気を入れてふくらますと、固い感じのものになります。 輪ゴムを引きのばしたときも固くなります。
ナスは黒光りのする弾力性をもったものですが、焼きナスビになると、水気たっぷりの柔らかいものになります。ナスが陰性の食物だといわれるのも、このように水気が多いところからでもあるわけです。ジャガ芋が陰性であるのは、食べるときに塩気が多くいることで分ります。サツマ芋が陰性であるのは、食べたらおなかが張ってガスが出やすいことからもいえるわけです。
のびる・しまる、ふくらむ・ちぢむということは、こうして食べものについて見ることができますし、料理の際にもそれが分り、食べてみると体でも知ることができるというものです。科学的栄養学が、こうした理を発見できたらすばらしいと思うのですが、ものごとを小さく分析して見る行き方からは、どうしてもそこまではいかないようです。ここに東洋の全体観的陰陽の見方の大切さがあるというものです。
7.冷やす食物、温める食物
砂糖が体を冷やす?
夏の暑いとき、冷ややっこや冷やしそうめんを食べると気分がスーッとします。冷たい麦茶もたしかに体を冷やしてくれます。また、冬の寒いときに熱い湯豆腐で一杯の酒を汲みかわし、アツアツのうどんを食べると体が温まってくるのは、だれしも経験ずみのことです。
しかし、これは材料を冷やしたり、温めたりしてのことですから当然というべきでしょう。マクロビオティックでは、そういうことも含めて、材料そのものの性質についてもいっています。たとえば、砂糖や果物は体を冷やし、塩や根菜類は体を温めるなどというのです。そうなると「それはおかしいではないか、栄養学ではそんなことはいわないし、砂糖の糖分はカロリーが高く、体内で燃焼してエネルギーに変わるものなのに、どうしてそういえるのか」という疑問をもつ人もあるでしょう。
ブドウ糖の注射をすると、体がカーッと熱く感じます。ブドウ糖という糖分がいちはやく体内で燃焼するからです。こうしたところから、多くの人は「疲れたときには甘いものを食べたら元気になる」と信じ込んでいます。しかし、ここには大きな考え違いがあります。たしかに、ブドウ糖の注射が体を活性化し、甘い砂糖をとったら元気がつくように感じるものですが、それはホンのひとときでしかありません。マッチの炎が燃えてすぐ消えるようなものなのです。まず、私たちは砂糖やそのブドウ糖の糖分が、人間の体に必要欠くべからざる糖とは異なることを知る必要があります。
糖分にもさまざまな違いがある
糖分には米や麦のような穀物の糖分もあれば、タマネギやゴボウやニンジンのような野菜の糖分、サツマ芋やジャガ芋のような芋類の糖分、果物の糖分、蜂蜜の糖分、砂糖の糖分、そして合成甘味料の糖分もあるのです。これらは同じく糖分といっても、それぞれに性格が異なるものです。ごはんやうどんはよく噛んで唾液がまざると、分解して甘い糖分に変わります。
タマネギやゴボウやニンジンは生のときと、油で炒めて煮たときとは甘さが断然違います。油で炒めて煮たものは、まるで砂糖をまぶした甘さになります。これらの穀物や野菜の糖分は、それらが重要な食物であるだけに人体に貴重なものです。サツマ芋は焼いたり蒸かしたりしたら、ずいぶん甘くなります。サツマ芋やジャガ芋からは飴をつくります。子ども向けの飴や飴玉はほとんどこれら芋飴です。
果物は汁気の多いもので、ずいぶん甘味があります。果物の糖分は栄養学では果糖とよばれます。果物は大切な食物といわれますが、ほんとうは嗜好食であって、日本ではぜひとも取らねばならぬ必要食ではありません。蜂蜜はミツバチが植物の頂上(▽)に咲く花の中の▽性な蜜を集めてできた糖分で、もともとは薬用に用いたものです。
砂糖は甘蔗をしぼって精製した糖分です。甘蔗は亜熱帯または熱帯産のものですから、日本のような温暖な地には向いたものではないわけです。ただ、その甘味の強さが人に愛好されるわけで合成甘味料の糖分は化学的なもので、天然自然のものではありませんから、人体には不向きなものというべきです。
砂糖が体を冷やすわけ
糖分の性格が違うのは、その生い立ちや性質が異なるからです。正食で砂糖をとくに問題にし、声を大にして警告を発するのは、そのとり過ぎが歯を悪くし、目を近視にし、鼻を蓄膿症にし、体内のカルシウム分とむすびついて、体外に流し去ってしまい、筋肉や臓器や、骨まで弱めてしまうからです。いいかえれば、体全体を陰性にゆるめてしまうからです。
甘蔗の生い立ちを見るのに、真夏の日本の炎暑が一年中つづく熱帯地を想像してみましょう。 カンカン、ジリジリと照りつける強烈な太陽熱のもとで、甘蔗は青々と繁っています。この炎天下に、もし私たちが半日間でも立ちつくしていたら、たちまち日射病で倒れてしまうでしょう。
そんな炎天下で甘蔗が青々と繁って平気なのは、甘蔗という植物の生理作用全体が、いわば冷蔵庫のような冷却作用の極陰の状態を保ってこそできるわけです。この点、バナナ、パイナップルもココナツもヤシの実もコーヒーの実も同じといえます。
「陽(△)は陰(▽)を生ず」は天地の法則です。従って、これら熱帯産の植物はその性質として、強い陰(▽)の要素をもっています。陰性の特徴は遠心性であり、拡散性であり、冷たさであり、ゆるみです。この陰性の性質が体をゆるめ、冷やす特徴はもう、根っからのもので、これを食べものとして簡単に陽性に変えるわけにはいかないものです。
青梅は酸っぱくて、そのままかじったりすると、歯が浮いたり、お腹が痛くなったりします。そのままでは強い陰▽性です。けれども、これを塩づけ(△)にし、真夏の炎天(△)の下で三日三晩外に出して、昼は太陽熱(△)を吸収させ、夜は冷たい夜気(▽)を吸いとらせてのち、ふたたびビンやカメに入れて、一年以上もの長い時間の△性を加え、△性食に変えて梅干にしたもので、毒を変じて薬にしたわけです。これは日本産のものですから、それだけの操作ができるのです。砂糖の▽極性に少々の熱を加えたからといって、その極性度を△性に変えることはとてもできるものではないのです。
果物はなぜ体を冷やすのか
果物もそのままでは水分が多いものであり、モモやナシやブドウやスイカやメロンは夏の△性の時季にとれる▽性なものであり、体の組織をゆるめ、従って冷やすことになるのです。ミカンは秋口にみのりますが、暖かい(△)性の地域にしか育たない(▽)性の果物です。
柿は渋柿(△)だと、とても食べられませんが、渋抜きをしたものや、皮をむいて干柿にすると甘く(▽)なります。しかし、その甘さも、渋抜きのものと熟柿の柔らかいものと干柿とは体に作用する度合は異なります。いちばん体を冷やすのは、水気のタップリたまった熟柿(▽)です。これを甘いからというので二つも三つも一度に食べたら、カゼをひいたり、ぜんそくを引き起こしたり、流産したりします。
塩気は体を温めるのだが
体を温めるものとしての筆頭は塩です。肉や魚には塩からくないナトリウムという塩分が入っていて、それを火という(△)性を加えたうえに塩気(△)を添えて食べるのですから、寒冷地や寒い時期には体を温める食物として向いているわけです。このごろ「塩をとりすぎるな」とよくいわれるようになりました。以前にはなかったことです。どうして急にそういわれるようになったかというと、塩分のとりすぎが高血圧のもとになるからだといいます。
しかし、なぜ急にそんなに高血圧症がふえたかを考える必要がありましょう。それは、もともと肉食をあまりしなかった日本人の肉食や魚食の量が、急増したからだといえるでしょう。肉食をして、塩気をへらしたにしても、野菜のとり方が少なく、果物や砂糖のとり方が多かったら、減塩の効果もたいして上がらないはずです。むしろ塩気不足になることもありましょう。
塩分はとりすぎると血管を引きしめて、血流を困難にさせ、高血圧の原因になりましょうが、そこには肉や卵や魚のもつ塩からくない塩分のとりすぎがありうることを、念頭においておく必要があるというものです。ゴボウやニンジンやレンコンなどの根菜類は、太陽の性にそむいて、暗い地中の水分の▽性を求めてのびるほど△性なもので、ナトリウム分が葉菜よりも多く、体を引きしめ、温めることになります。けれども、動物性食品の陽性度よりははるかに陰性です。
病気は体全体が▽性になって活気を失った状態ですが、そうなるについても、▽性の砂糖や果物などのとりすぎによる場合と、△性な肉食や塩分のとりすぎで血管がしまりすぎ、血流を悪くして活気を失い、▽性になった場合との二つの傾向がありえますから、いちがいに病気だからといって、△性にしようとして食を心がけるのも、当をえたものとはいえません。△性過多の場合には、むしろたとえば、青い葉っぱや果物などの▽性食を多くとるべきなのです。
※山口卓三『陰陽でみる食養法』第5章より
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(引用ここまで)
この続きはまた明日!
【易経関連の主な過去投稿記事】
・わたしが易経から学んだこと
・易経というモノサシをどう活用できるか
・易経の歴史学への応用ーーー文明法則の発見について
・ユング「易は自ら問いを発する人に対してのみ己自身を開示する」(今日の名言・その79)