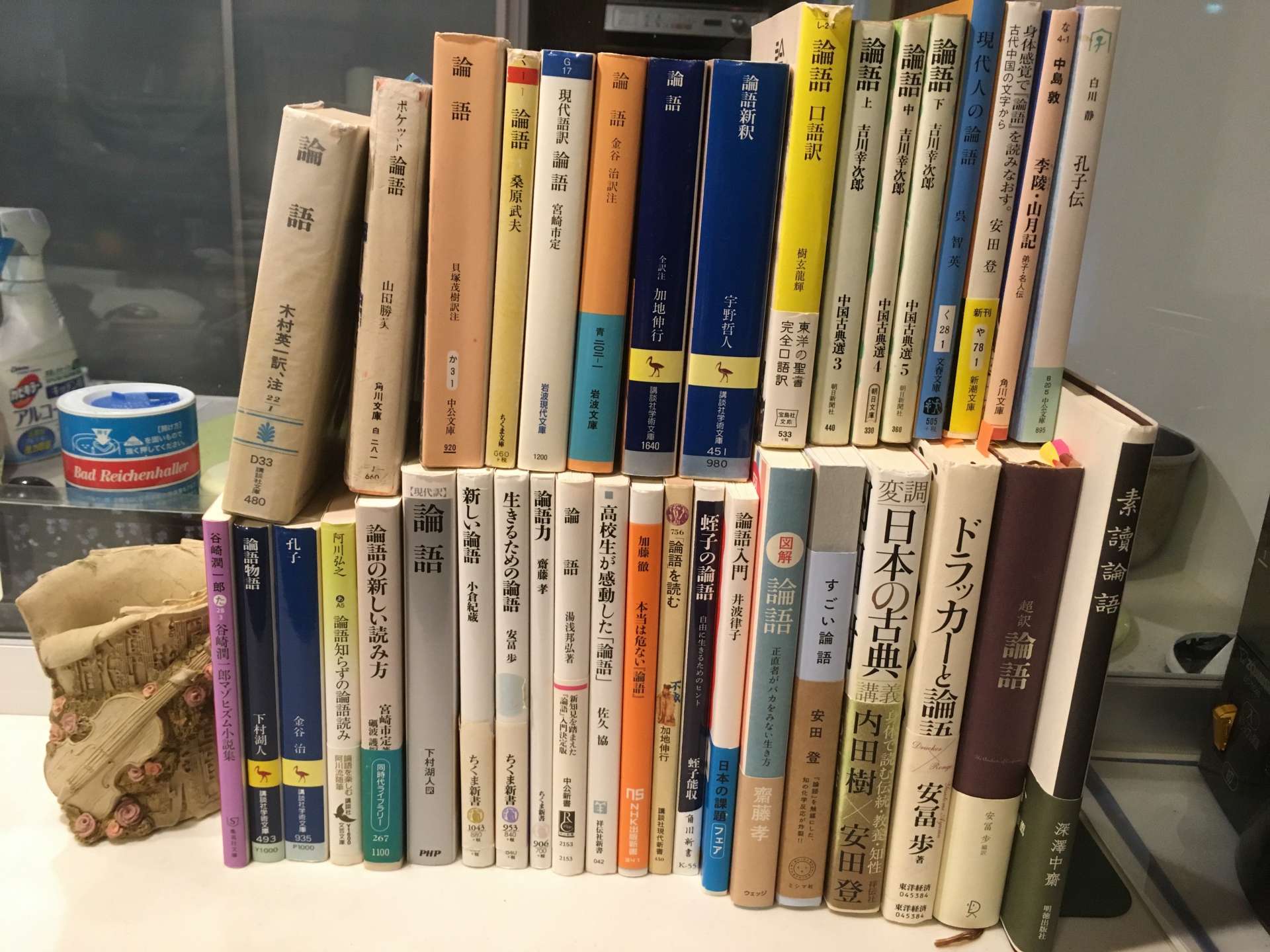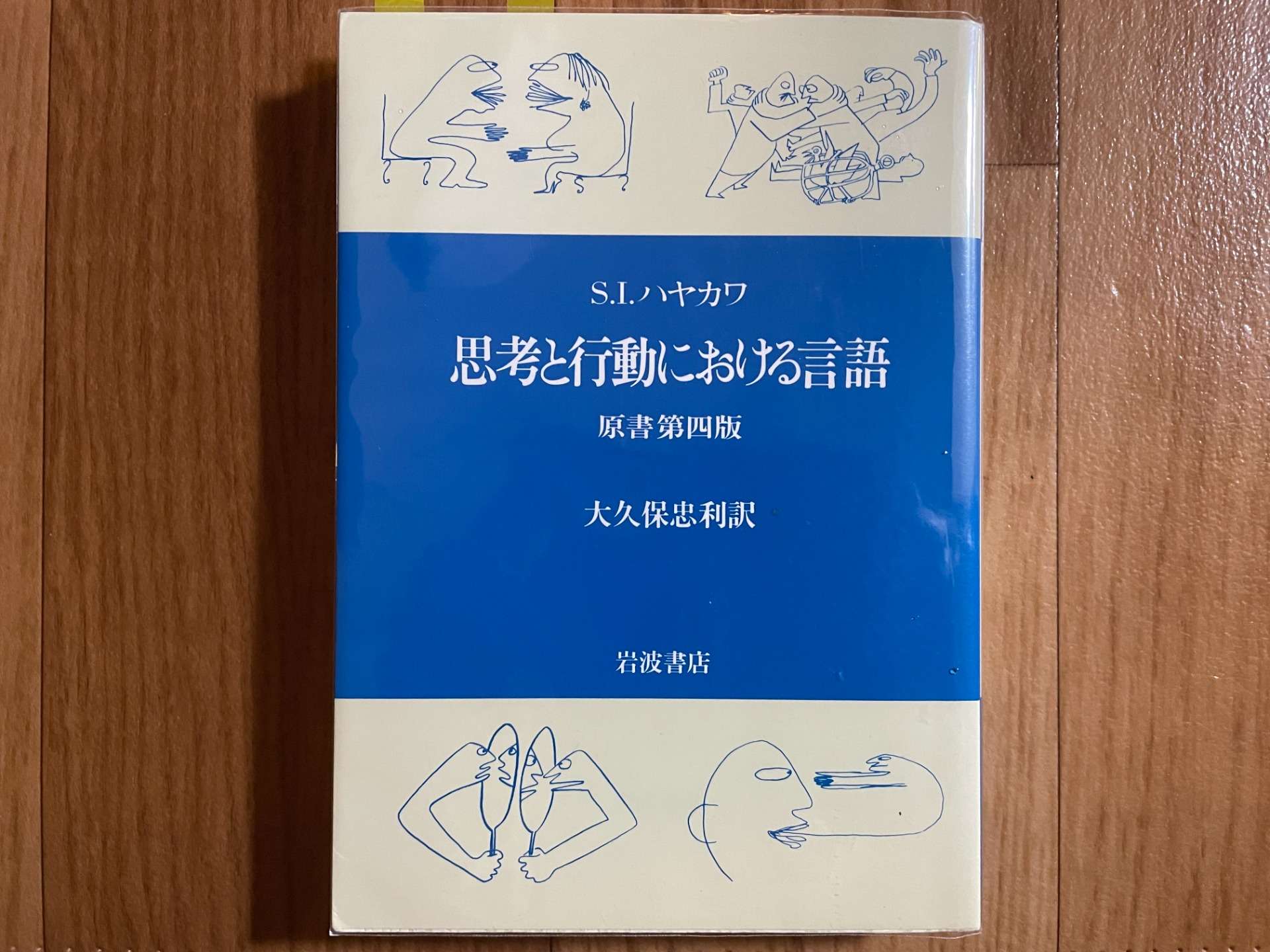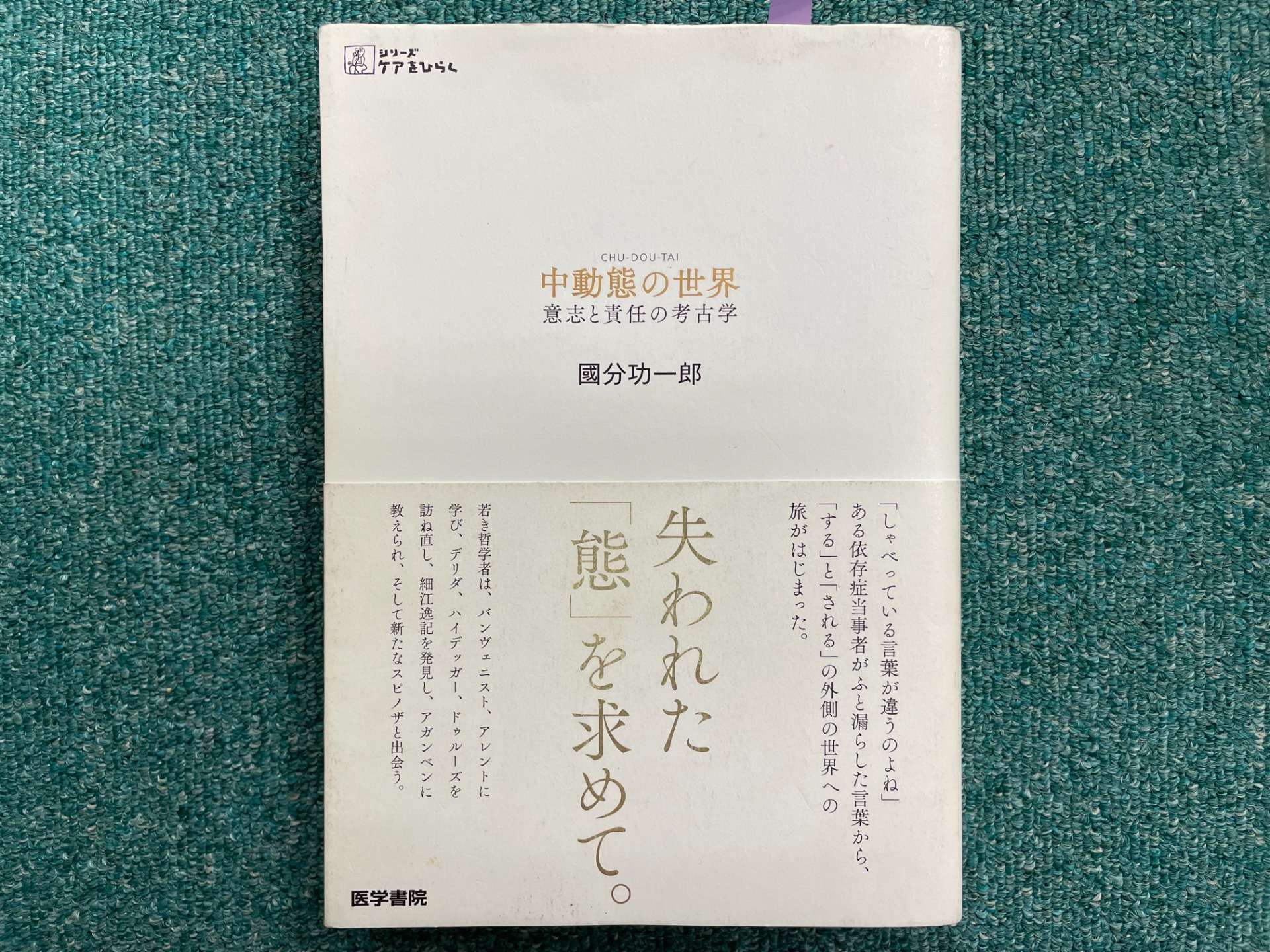君子有九思、視思明、聽思聰、色思溫(「論語499章1日1章読解」より)+INDEX
2023/09/09
昨日に続いて今日も論語499章読解からの記事で、
今月はこれで7回目になりました。
別のテーマで書きたい記事もあるので
そろそろ一区切りにしようと考えています。
論語499章読解の記事は、タイトルのつけ方など
最初から統一されていませんし、
また、2年にわたってランダムに選んで、
投稿してきてタイトルに通し番号も
入れていませんでしたので、
これまでの投稿が検索しやすいように
本日分の記事のあとにINDEXをつけ、
また、論語読解に参考になりそうな記事も
リストアップしてシェアすることにしましたので、
ご活用ください。
さて今日は、孔子が君子が行動するにあたって
気をつけるべきことがらを9つにまとめた
季氏第十六の10番(通し番号430)です。
コメントのところに記したように、
本章はおそらく季氏篇の他の章と同じく
戦国時代以降に儒者によって創作され、
孔子本人の言葉でない可能性が高いものです。
とはいえ、その中味は孔子の言葉をもとに
編集されたものであることは間違いないので、
孔子本人の言葉でないからと言って、
その価値を大きく貶めるものではないように
感じました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【季氏・第十六】430-16-10
[要旨(大意)]
君子として留意すべき九思について孔子が述べている章
[白文]
孔子曰、君子有九思、視思明、聽思聰、色思溫、貌思恭、言思忠、事思敬、疑思問、忿思難、見得思義。
[訓読文]
孔子曰ク、君子ニ九思有リ、視ハ明ヲ思ヒ、聽ハ聰ヲ思ヒ、色ハ溫ヲ思ヒ、貌ハ恭ヲ思ヒ、言ハ忠ヲ思ヒ、事ハ敬ヲ思ヒ、疑ハ問ヲ思ヒ、忿ハ難ヲ思ヒ、得ルヲ見テハ義ヲ思フ。
[カナ付き訓読文]
孔子(こうし)曰(いわ)ク、君子(くんし)ニ九思(きゅうし)有(あ)リ、視(みる)ハ明(めい)ヲ思(おも)ヒ、聴(きく)ハ聡(そう)ヲ思(おも)ヒ、色(いろ)ハ温(おん)ヲ思(おも)ヒ、貌(かたち)ハ恭(きょう)ヲ思(おも)ヒ、言(げん)ハ忠(ちゅう)ヲ思(おも)ヒ、事(こと)ハ敬(けい)ヲ思(おも)ヒ、疑(うたがい)ハ問(とい)ヲ思(おも)ヒ、忿(いかり)ハ難(なん)ヲ思(おも)ヒ、得(う)ルヲ見(み)テハ義(ぎ)ヲ思(おも)フ。
[ひらがな素読文]
こうしいわく、くんしにきゅうしあり、みるはめいをおもい、きくはそうをおもい、いろはおんをおもい、かたちはきょうをおもい、げんはちゅうをおもい、ことはけいをおもい、うたがいにはといをおもい、いかりはなんをおもい、うるをみてはぎをおもう。
[口語訳文1(逐語訳)]
孔子が言われた。「君子には九つの思うことがある。観察するときにははっきり見たいと思い、聞くときには細かく聞きたいと思い、顔つきは穏やかでありたいと思い、姿には恭しくありたいと思い、言葉には誠実でありたいと思い、仕事には慎重でありたいと思い、疑わしいことには質問することを思い、怒りには後々の困難を思い、利益を得るときには筋が通っていることを思う。」
[口語訳文2(従来訳)]
先師がいわれた。――
「君子には九つの思いがある。見ることは明らかでありたいと思い、聴くことは聡くありたいと思い、顔色は温和でありたいと思い、態度は恭しくありたいと思い、言語は誠実でありたいと思い、仕事は慎重でありたいと思い、疑いは問いただしたいと思い、怒れば後難のおそれあるを思い、利得を見ては正義を思うのである」(下村湖人『現代訳論語』)
[口語訳文3(井上による意訳)]
君子には九つの思慮がある。物事を視るにつけてははっきり見分けるようにと思慮し、人の話を聴くにつけてはよく聞き分けるように思慮し、顔色は穏和であるように思慮し、容姿態度は恭順であるように思慮し、言葉は忠信であるように思慮し、仕事は鄭重に取り扱うよう思慮し、不確かなことがあれば質問して解決するように思慮し、怒りを感じたときには後先で難儀が起こらぬように配慮し、利益を得る前に、それを受け取ることが正義にかなっているかどうかを思慮する。
[語釈]
思:~に際して思うべきこと。
視:観察する、真っ直ぐに見ること。
明:白日の下にさらしたようにあきらかであること。
聴:真っ直ぐに聞くこと、直接聞くこと。ちなみに聞は、間接的に聞く意味。
聰:分かりが早いこと、聡明なようす。
色:顔つき、表情。
温:温かい、温和な。
貌:立ち居振る舞い、所作、行動によって他者に見える姿。
恭:丁寧で慎み深い、うやうやしい様子。
言:言葉、発言、言ったこと。
忠:心に偽りがないこと。
事:仕事。
敬:心身を引き締めて丁寧にすること。
疑:疑わしいこと”。甲骨文から確認できる古い言葉。
問:質問すること。
忿:急激にカッとなって怒ること、急にわき起こる怒り。
難:あとになってやってくる災難。
見:出現したものを目に止める。
得:利益を得ること、儲け話。
義:筋が通っていること。
[井上のコメント]
本章は、季氏篇の今までの流れから、この章自体は九去堂も指摘しているように、孔子の死後に後世の編集によって創作され、孔子自身の肉声そのままを書き留めたものではない可能性は捨てきれないものの、内容的に見たときは、君子が行動するときに注意すべき9つのことについて、直感的にイメージしやすい箇条書き風にまとめているという点において、極めて重要な章であるようにおもいました。
その内容とは、既出章ではたとえば、公冶長第五の14番(通し番号106)に「子曰ク、敏ニシテ學ヲ好ミ、下問ヲ恥ジズ。(孔文子は、頭の回転が良くて学問を好み、目下の者にも問うことを恥じなかった。)」とあり、また顔淵第十二の21番(通し番号299)には「事ヲ先ニシテ得ルヲ後ニスルハ、德ヲ崇フスルニ非ズヤ、其ノ惡ヲ攻メテ人ノ惡ヲ攻ムル無キハ、慝ヲ脩ムルニ非ズヤ、一朝ノ忿ニ其ノ身ヲ忘レ以テ其ノ親ニ及ボスハ、惑ニ非ズヤ。(仕事を先にして、利益を得るのは後にする、それが人格を高めることにつながるのではないだろうか。自分の欠点は責めても、他人の欠点を責め立てないのは、隠れた自分の欠点を改める事になるのではないかね? 一時の怒りに我を忘れて、親まで巻き込んでしまうのが矛盾ではないかね?)」とあり、憲問第十四の13番(通し番号345)では、「利ヲ見テハ義ヲ思ヒ、危キヲ見テハ命ヲ授ケ、久要平生ノ言ヲ忘レズンバ、亦以テ成人ト爲ス可シ。(利益を見て筋が通るかを思い、危機には命をかけ、普段の言葉を忘れないなら、実に立派な完成した人と言えるでしょう。)」というような表現になっていたわけです。
まだ他にもありますが、これら孔子の言いたいことを、こちらの記事のコメントで紹介した「サヌキ性、アワ性」という言葉を使って端的に要約するなら、「アワ的な態度で自分の内心によく問いかけながら行動せよ」と説いていると言ってよいでしょう。
また、本章については、吉川幸次郎など、『書経』(尚書)の「洪範篇」に登場する「五事」、すなわち「貌曰恭、言曰従、視曰明、聴曰聡、思曰睿。(一つに容貌、態度を恭しくし、二つに言行においてへりくだり争わず、三つにすべてをよく見透し、四つによく聞いてまちがわず、五つに深く綿密に思うことである。)」との関連性を説く人がすくなくありません。
[参考]
・日本の「思う」は漠然としていて、たんなる欲望も含まれる。中国古典語の「思」は、「考える」「反省する」「思索する」に限定して用いられる。ここでは、生活の経験に即して考慮することで、行動の前に、行動しつつ、また行動のあとで「どうだかな」と考えてみることをさす。(貝塚茂樹訳注『論語』より)
・論語詳解430季氏篇第十六(13)君子に九の思*(九去堂)
●論語499章1日1章読解 過去の投稿記事一覧
【為政・第二】020-2-04 吾十有五而志乎學、三十而立、四十而不惑
【八佾・第三】063-3-23 子語魯大師樂曰、樂其可知已、始作翕如也
【里仁・第四】073-4-07 人之過也、各於其黨、觀過斯知仁矣
【里仁・第四】077-4-11 君子懐德、小人懷土、君子懷刑、小人懐惠
【雍也・第六】129-6-10 冉求曰、非不説子之道、力不足也
【雍也・第六】136-6-17 人之生也直、罔之生也、幸而免
【雍也・第六】146-6-27 中庸之爲德也
【雍也・第六】147-6-28 子貢曰、如能博施於民、而能済濟衆、何如
【述而・第七】148-7-1 述而不作、信而好古、竊比於我老彭
【述而・第七】163-7-16 如我數年、五十以學、易可以無大過矣
【述而・第七】170-7-23 二三子以我爲隠乎、吾無隠乎爾
【子罕・第九】215-9-10 顔淵喟然歎曰、仰之彌高、鑽之彌堅、瞻之在前
【子罕・第九】228-9-23 法語之言、能無從乎、改之爲貴
【子罕・第九】234&235-9-29&30 可與共學、未可與適道、可與適道
【顔淵・第十二】279-12-1 顔淵問仁、子曰、克己復禮爲仁
【子路・第十三】323-13-21 不得中行而與之、必也狂狷乎
【子路・第十三】324-13-22 南人有言、曰、人而無恆、不可以作巫醫
【子路・第十三】328-13-26 君子泰而不驕、小人驕而不泰
【憲問・第十四】337-14-5 有德者必有言、有言者不必有德
【衛霊公・第十五】381-15-2 賜也、女以予爲多學而識之者與
【衛霊公・第十五】384-15-5 子張問行、子曰、言忠信、行篤敬、雖蠻貊之邦行矣
【衛霊公・第十五】396-15-17 君子義以爲質、禮以行之、孫以出之、信以成之
【陽貨・第十七】443-17-9 小子、何莫學夫詩、詩可以興
【季氏・第十六】429-16-9 生而知之者、上也、學而知之者、次也
【堯曰・第二十】499-20-3 不知命、無以爲君子也、不知禮
※通し番号155と228、163と324は
一つの記事にて紹介しています。
【参考記事】
・顔回をめぐる問いと諸星大二郎『孔子暗黒伝』のこと
・安田登『役に立つ古典』〜古典から何を学ぶか〜
・情報洪水の時代をどう生きるか(その6)