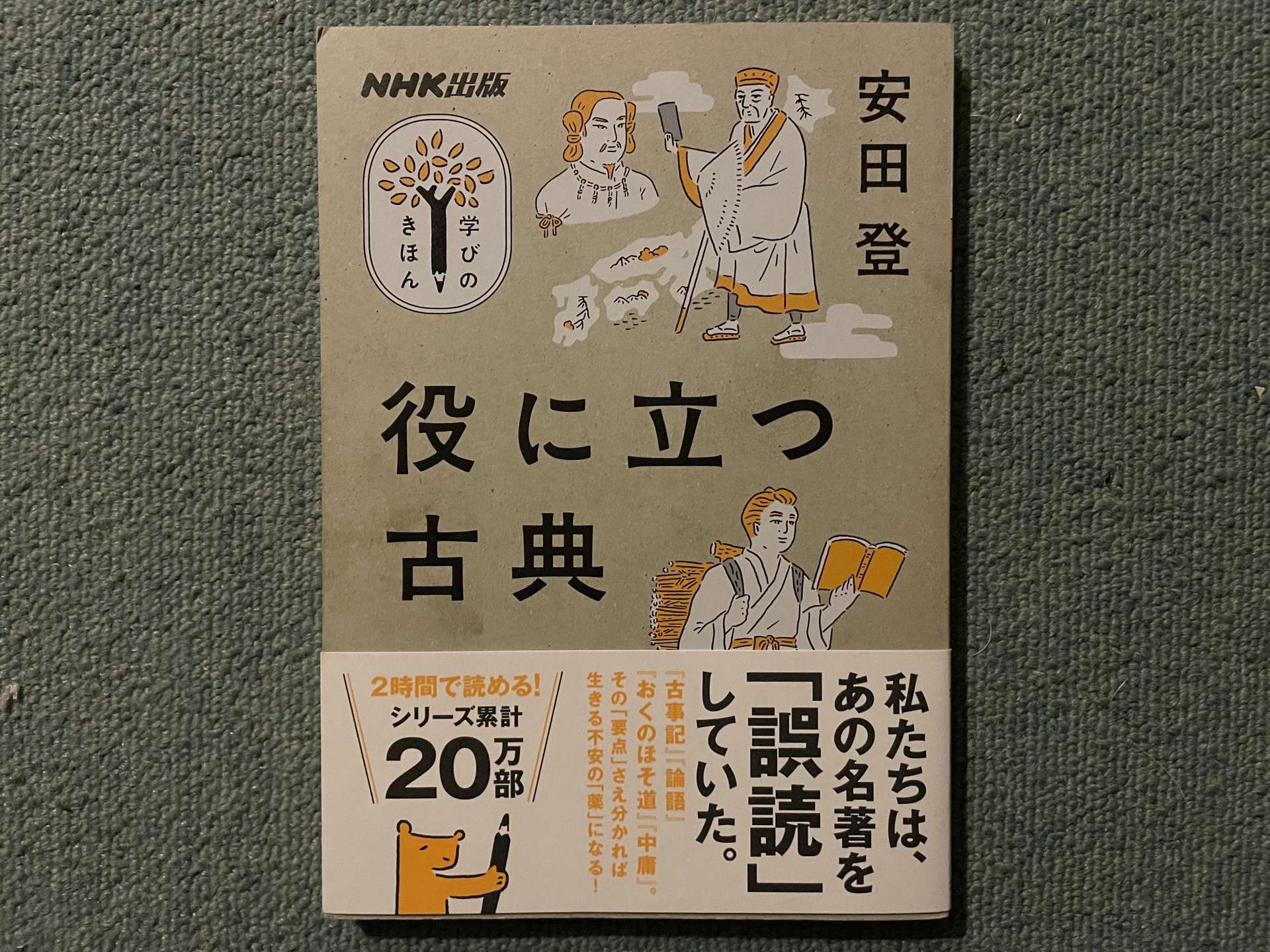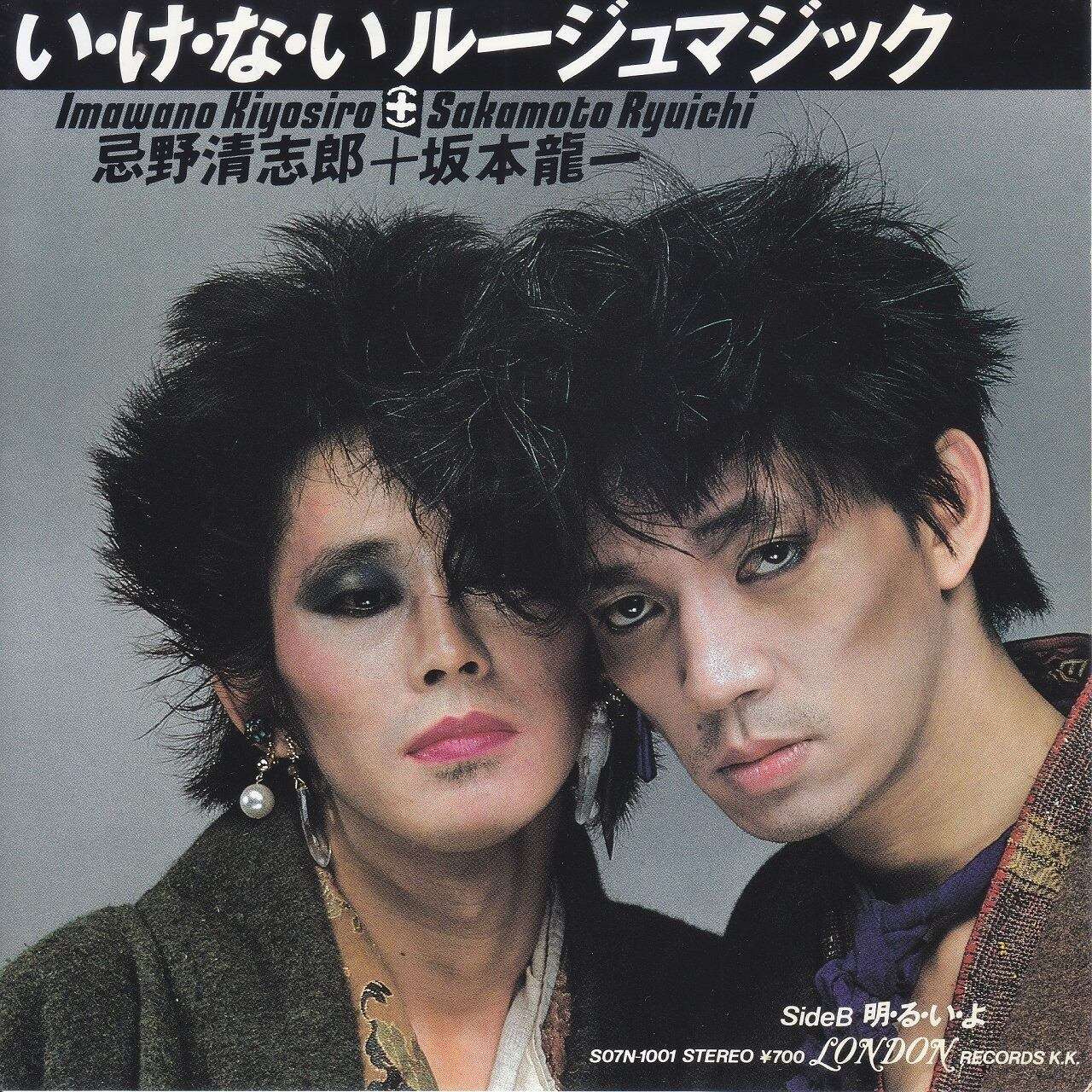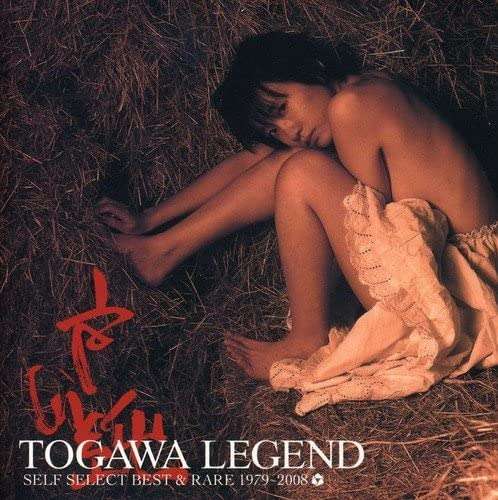本当の「切磋琢磨」(安田登『役に立つ古典』より)
2024/05/18
今月は論語月間というか、
論語499章1日1章読解から、
昨日まで10回続けて投稿してきました。
・不曰如之何如之何者(『論語』衛霊公第十五の15 No.394)
・學如不及、猶恐失之(『論語』泰伯第八の17 No.201)
・性相近也、習相遠也(『論語』陽貨第十七の02 No.436)
・我未見好仁者惡不仁者(『論語』里仁第四の04 No.072)
・子貢問君子、子曰、先行其言(『論語』為政第二の13 No.029)
・中人以上可以語上也(『論語』雍也第六の19 No.138)
・子所雅言、詩書執禮(『論語』述而第七の17 No.164)
・質勝文則野、文勝質則史(『論語』雍也第六の16 No.135)
もうしばらくの間このスタイルの投稿を
続けるつもりでいるんですが、
ずっと古典文を読み解くのも
なかなかタイトでしょうから、
本日はインターミッションというか、
ちょっとひとやすみの投稿を。
以前も次の記事で紹介したことがあるんですが、
2019年7月に学びのきほんシリーズから出版された
安田登『役に立つ古典』より引用して
論語のような古典を、
現代に生きるわたしたちのような人間が
どのように読めばよいのかについて、
「切磋琢磨」という言葉の意味について
説明されている箇所を、
寺子屋塾の学習内容にも絡めつつ
ご紹介しようとおもいます。
ちなみに、安田さんは、
論語の中でも最も有名な章のひとつ、
為政第二の4(通し番号020)の〝四十而不惑〟を
「四十歳になってもひとつの枠に納まることなく
はみ出していた」と訳された方で、
そのことについては、
次の論語499章1日1章読解記事で触れました。
【為政・第二】020-2-04 吾十有五而志乎學、三十而立、四十而不惑
(引用ここから)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
本当の「切磋琢磨」
続いて、人間関係の悩みに対するヒントになる言葉を二つ紹介します。
ひとつ目は「切磋琢磨」です。「仲間が競い合って向上する」という意味でいまもよく使われる言葉ですね。この四字熟語は『論語』の次のエピソードに由来しています。
孔子の弟子でお金持ちの子貢が、孔子に質問します。「貧しくても卑屈にならず、富んでも驕ることがないのはどうでしょう」。孔子は「まあ、いいだろう。でも、貧しくても道を楽しみ、富んでも礼を好む者にはかなわないな」と答えます。子貢は「なるほど、それが『詩経』でいうところの切磋琢磨なんですね」と応じます。すると孔子は、「おお、これでお前とはじめて『詩経』について語ることができるな。お前は『往』を告げれば『復』で返す者だ」と言うのです。私が話したこと(往)を、自分自身の体験に照らして(復)考えることができる者だと認めたのです。
なんとも不思議なやり取りですね。しかし、このエピソードにこそ「切磋琢磨」の本当の意味が示されているのです。
東洋学者の貝塚茂樹氏によれば、「切」とは骨を削って器をつくること、「磋」は象牙を加工すること、「琢」は玉を擦ること、「磨」は石を磨くことだといいます。つまり切磋琢磨とは、あるものに手を加えて付加価値のあるものをつくることなのです。しかし、たとえばダイヤモンドを磨く研磨機で真珠を磨いたら、真珠は台無しになってしまいます。それぞれの原石には、それぞれを磨くためのツールがあるのです。
つまり、切磋琢磨とは「その人のあり方に合ったやり方で自分を磨く」ということです。
孔子のグループは清貧をよしとしていました。しかし、子貢はお金持ちです。お金持ちの彼には、彼なりの引け目があったのでしょう。
しかし、子貢がお金持ちなのは彼がお金持ちに向いているからです。清貧の人は貧乏が好きだから貧乏でいる。なおその立場で「道」を目指すのがよい。お金持ちの子貢はお金持ちとして道を求めればいいのです。他人と比べてこうすべきだと考えるのは苦しい。その人にもともと備わっているよいところを磨いて伸ばすことが大切だ。そう言っています。
第4章で取り上げる『中庸』に「天の命ずるをこれ性と謂う」という言葉があります。人にはそれぞれが天から与えられた素材としての「性」がある、という意味です。他人の「性」に合った方法ではなく、自分の「性」に合った方法で道を探求する。孔子はそれを勧めています。他人と比べる必要はありません。
※安田登『役に立つ古典』第2章『論語』が示す「心」の道しるべ P.42〜44 より
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(引用ここまで)
皆さんは、「切磋琢磨」という言葉を
これまでどのような意味で使われていましたか?
寺子屋塾での学びスタイル、
セルフラーニングとは、まさに
上に引用した箇所で安田さんが述べている
「その人のあり方に合ったやり方で自分を磨く」を
大事にする学習なんですね。
自分に合った自分を磨くやり方というのは、
その人にもともと備わっているものであっても、
一人ひとり異なりますから、
指導者のわたしが
一方的に教えられないのはもちろん、
実際に学習を進めながら、
対話的なやりとりを重ねながら
学習者自身が見つけていくしかありません。
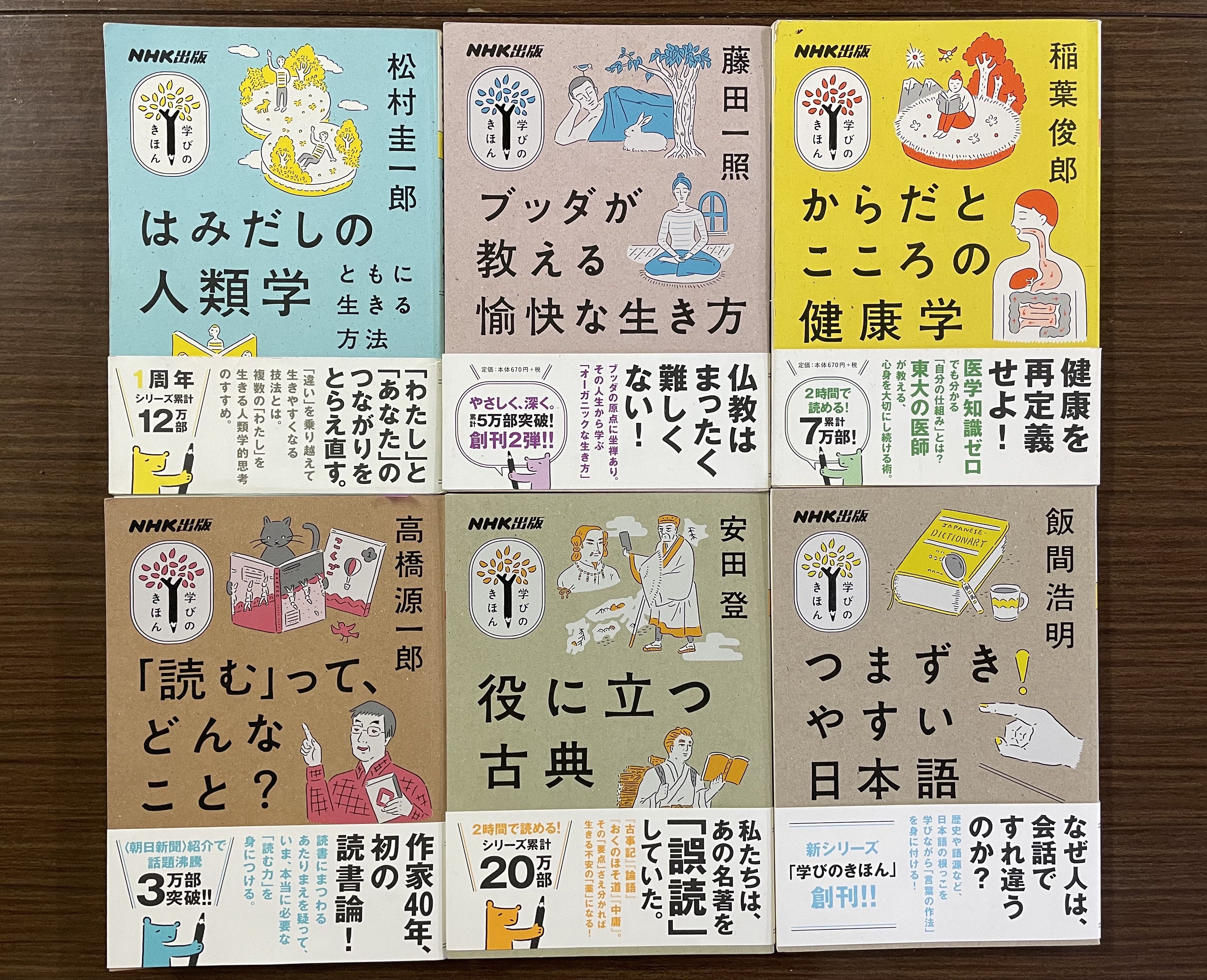
「学びのきほん」シリーズについては
以前にも次の記事で紹介したことがあるんですが、
とてもよく考えて編集されていて
本当にハズレが無いんですね。(既刊23冊)
安田さんのこの本は、
単なる作品の解説ではなく、
どのように古典作品と向き合えばよいか、
そうした姿勢、心構えがとても参考になりますよ。
●論語499章1日1章読解 過去の投稿記事一覧
【為政・第二】020-2-04 吾十有五而志乎學、三十而立、四十而不惑
【八佾・第三】063-3-23 子語魯大師樂曰、樂其可知已、始作翕如也
【里仁・第四】072-4-04我未見好仁者惡不仁者(『論語』里仁第四の4 No.72)
【里仁・第四】073-4-07 人之過也、各於其黨、觀過斯知仁矣
【里仁・第四】076-4-19 君子之於天下也、無適也、無莫也、義之與比
【里仁・第四】077-4-11 君子懐德、小人懷土、君子懷刑、小人懐惠
【里仁・第四】084-4-18 事父母幾諌、見志不從、又敬不違、勞而不怨
【雍也・第六】129-6-10 冉求曰、非不説子之道、力不足也
【雍也・第六】136-6-17 人之生也直、罔之生也、幸而免
【雍也・第六】138-6-19 中人以上、可以語上也、中人以下、不可以語上也
【雍也・第六】146-6-27 中庸之爲德也
【雍也・第六】147-6-28 子貢曰、如能博施於民、而能済濟衆、何如
【述而・第七】148-7-01 述而不作、信而好古、竊比於我老彭
【述而・第七】163-7-16 如我數年、五十以學、易可以無大過矣
【述而・第七】170-7-23 二三子以我爲隠乎、吾無隠乎爾
【子罕・第九】215-9-10 顔淵喟然歎曰、仰之彌高、鑽之彌堅、瞻之在前
【子罕・第九】228-9-23 法語之言、能無從乎、改之爲貴
【子罕・第九】234&235-9-29&30 可與共學、未可與適道、可與適道
【顔淵・第十二】279-12-01 顔淵問仁、子曰、克己復禮爲仁
【子路・第十三】323-13-21 不得中行而與之、必也狂狷乎
【子路・第十三】324-13-22 南人有言、曰、人而無恆、不可以作巫醫
【子路・第十三】325-13-23 君子和而不同、小人同而不和
【子路・第十三】328-13-26 君子泰而不驕、小人驕而不泰
【憲問・第十四】337-14-05 有德者必有言、有言者不必有德
【衛霊公・第十五】381-15-02 賜也、女以予爲多學而識之者與
【衛霊公・第十五】384-15-05 子張問行、子曰、言忠信、行篤敬、雖蠻貊之邦行矣
【衛霊公・第十五】396-15-17 君子義以爲質、禮以行之、孫以出之、信以成之
【季氏・第十六】429-16-09 生而知之者、上也、學而知之者、次也
【陽貨・第十七】443-17-09 小子、何莫學夫詩、詩可以興
【堯曰・第二十】499-20-03 不知命、無以爲君子也、不知禮
●論語読解の参考になる過去投稿記事
・情報洪水の時代をどう生きるか(その6)
・顔回をめぐる問いと諸星大二郎『孔子暗黒伝』のこと
・書経・商書「生きる方向軸が一つに定まっていれば吉」(「今日の名言・その7」)
・問題解決ツールのコレクターになっていませんか?(つぶやき考現学 No.59)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●2021.9.1~2023.12.31記事タイトル一覧は
こちらの記事(旧ブログ)からどうぞ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
☆寺子屋塾に関連するイベントのご案内
6/16(日) インタビューゲーム4hセッション